※この記事は『Mac Fan』2023年6月号に掲載されたものです。
Macで作曲に励む宮本佳林さんには、気になるDTMツールがいっぱい!第16回はIK Multimediaのリファレンス・モニターを試聴しました。

宮本佳林
歌手。ハロー!プロジェクト所属の女性アイドルグループ・Juice=Juiceの元メンバー。現在はソロ名義で活躍の場を広げている。趣味はアニメ・漫画鑑賞、射撃(シューティング)。

「iLoud Micro Monitor」はバッグに入るくらいコンパクト。自宅など、狭い環境向けに設計しているんだって!
今回は音響や映像に関するソフトウェア・ハードウェアの輸入販売を行う株式会社フックアップで、IK Multimediaでアジア市場を担当している田村示音さんに「iLoud」シリーズのスピーカについて教えてもらいました。
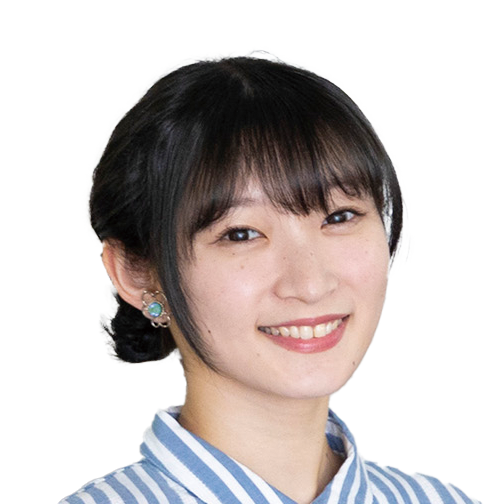
宮本佳林
IK Multimediaはどんなメーカーなんですか?

田村示音
イタリアのモデナに本社がある、オーディオソフトやハードウェアを開発する会社です。
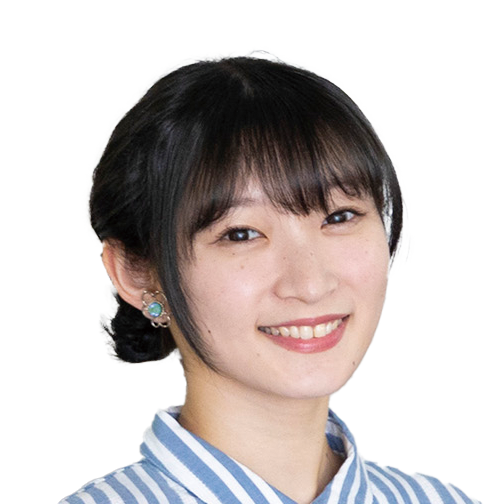
宮本佳林
iLoudはどういったシリーズなんでしょうか。

田村示音
リファレンス用モニタースピーカで、最初に発表したのが、左右一体型のポータブルなモデルでした。次に出たのが、今回紹介する「iLoud Micro Monitor」です。
iLoud Micro Monitor

- 【発売】
- IK Multimedia
世界最小クラスのリファレンス・ モニター・システムとして人気の「iLoud Micro Monitor」。色つけがなく、透明感のあるクリアな音質が特徴です。さまざまな環境でスタジオクオリティのモニタリング環境を実現できます。
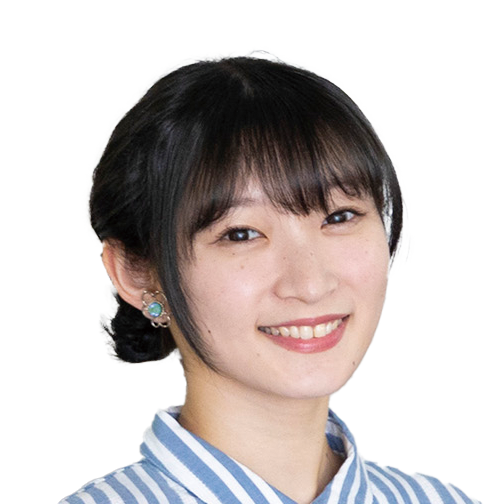
宮本佳林
すごくコンパクトですね。

田村示音
iLoudはまさにDTM、特に個人のデスクトップでの作業に最適です。それまでは、個人宅など狭い空間でのリファレンスに向いたモニタースピーカがなかったんですよ。

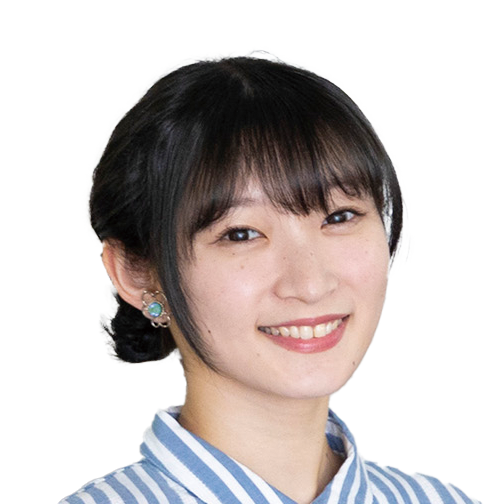
宮本佳林
私も押し入れを改造した秘密基地みたいなスペースで作曲していて、大きいスピーカは絶対使えない環境です…。

田村示音
大きいスピーカだと、それなりに距離をとらないと音のベストポジションにならないんですよね。50センチくらい離れた程度では、高音のツイータと低音のウーファから出る音がバラバラの状態で耳に届くんです。それを、脳で勝手にミックスして聞くことになります。
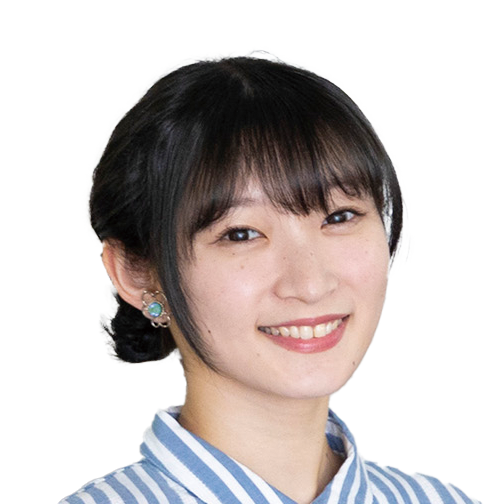
宮本佳林
そうなんですね! 脳ってすごい…。

田村示音
さらに低音と高音を分けて出すツーウェイ方式だと、ツイータのほうが反応が速く、ウーファの音が遅れて耳に届くんです。だからオーディオマニアの中には、低音から高音まで一つのドライバユニットで音を出すフルレンジスピーカのほうがいい、と言う人もいます。
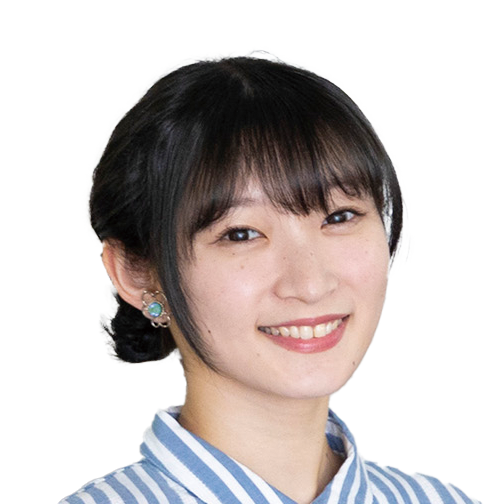
宮本佳林
タイミングの違いも脳が補正してるんですか?

田村示音
そうなんです。だから、長時間作業していると疲れてしまう。「iLoud Micro Monitor」は、小さいからスピーカの近くで聞いてもベストポジションになりますし、ツーウェイ方式の問題もアンプの鳴るタイミングをデジタル上でコントロールしてクリアしています。

小さくたってサウンドはパワフル。“味付け”しない音だからDTMには最適なんだ!
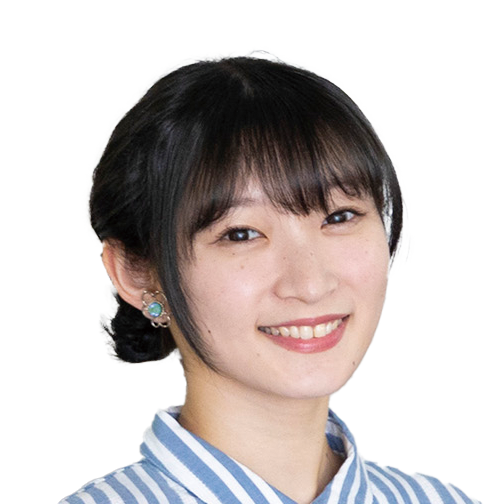
宮本佳林
背面のEQ(イコライザ)のところにある「FLAT」「DESK」という切り替えスイッチはなんですか?

田村示音
通常、スピーカを机の上に置くと、出た音が机の天板に跳ね返って低音がだぶついて聞こえるんです。「DESK」をオンにすると、跳ね返った音をカットしてスッキリ聞こえます。
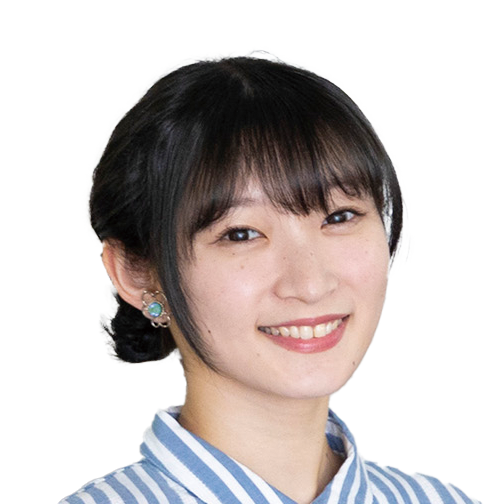
宮本佳林
そんな調整もしてくれるんですか!

田村示音
ソフトウェア開発の歴史が長いメーカーで、イコライザやコンプレッサなどのプラグインを作ってきたんですよね。その技術が活かされています。

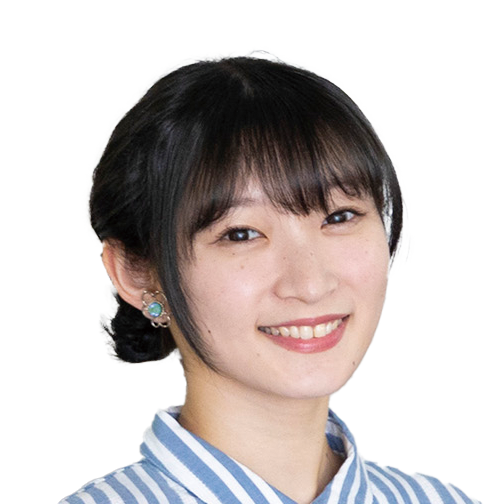
宮本佳林
小さいとあまり音量が出ないイメージがあるんですけど、そこはどうですか?

田村示音
聴いてみましょうか。ブルートゥースで接続して、好きな曲を流してみてください。
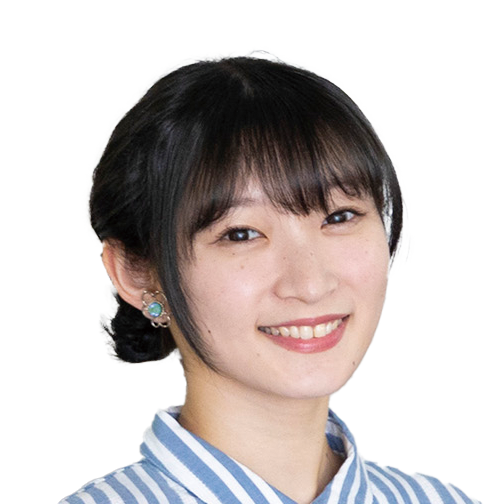
宮本佳林
じゃあ自分の曲を…なんて大きな音! これだけ鳴ったら路上ライブができそう(笑)。

田村示音
マイクスタンドにも取り付けられるので、インストアライブなどで使う方もいらっしゃいます。小さいスピーカで大音量を出そうとすると音が歪むことがあるのですが、デジタル上でコントロールしてそれを防いでいます。パワーが大きいうえに、45Hzから22kHzまでと鳴らせるレンジが広いんです。
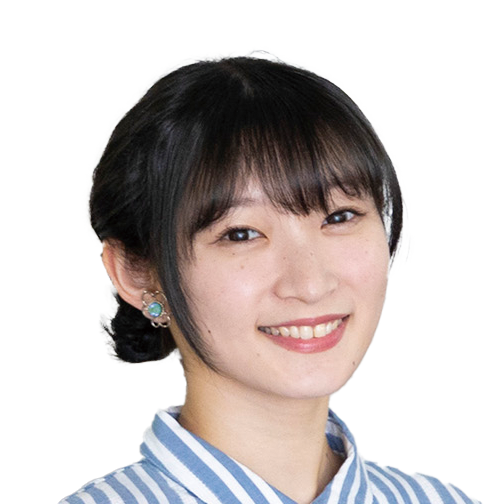
宮本佳林
ひとつひとつの音が鮮明に聞こえます。楽器の音がくっきりしてる…!


田村示音
リスニング用スピーカは低音や高音が強めに聞こえて気持ちいいですが、iLoudの音はフラットで別の気持ちよさがありますよね。日常的に使うことで自分の中に音の基準ができますよ。
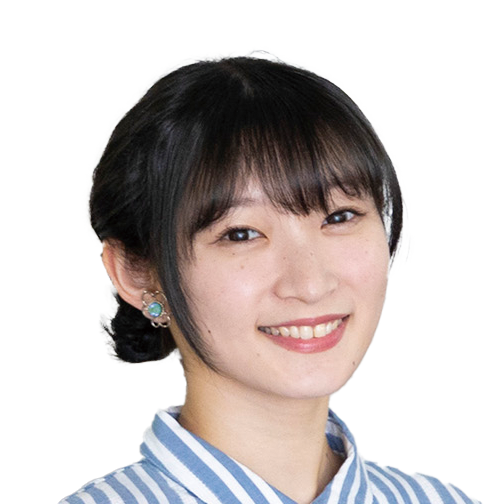
宮本佳林
ミックスでどういう調整をすればいいか、判断できるようになるんですね。こういうのって独学でとりあえず作曲を始めた人にはわからないことだから、教えてもらうのは大事。私も普段から「味付け」しない音で音楽を聴いてみようっと!





