チャット、静止画、動画と生成AIの進化には目覚ましいものがあり、今や1枚のイメージから3Dデータまで生成できるようになりました。
3D化は写真やイラストでも可能ですが、筆者は、普段、平面として認識されている絵文字が立体になったら面白そうだと思い、3Dデータを作って3Dプリンタで実体化してみることにしました。
最初に、3D化に使う「Tripo」の概要をAI生成した画像を使って説明し、次に絵文字の3D化、そして、iPhoneの「写真」アプリの被写体抽出機能を活用した埴輪や土偶のミニチュア制作にもトライしています。
モデリングなしに3Dデータを作れるTripo
かつて、3Dプリンタなどでミニ四駆をカスタマイズして競争させる「Fabミニ四駆(後にFabRacers)」というレースに参戦していた筆者は、1年ほど前にも、イメージを立体化できるという生成AIを試したことがありました。
しかし、その時点では、キャラクターやフィギュア的なものはそこそこ上手く生成できましたが、クルマのような造形物は、かろうじて輪郭がそれらしく見える程度のデータにしかならず、応用を諦めた記憶があります。
しかし、今回利用したTripoは、そこそこ精度の良い3Dデータを1〜2分(サーバ負荷が高いせいか、公称値の数秒よりもかなり長いですが、それでもこの程度で生成されるのは驚きです)で生成できる能力があるため、ホビー用途などに十分使えるサービスです。

しかも、無料プランでも毎月600クレジット(上限)が与えられるので、3Dデータの生成(1回あたり25クレジット消費)のみであれば、24回も生成することができます。
有料プランでは優先的に生成されたり、高解像度のテクスチャーマッピングが行われるようになりますが、そもそも一般的な3Dプリンタでは1色のみでのプリントになるので、テクスチャーマッピングの解像度は無関係です。
より多くの3Dデータ生成が必要だったり、3Dデータをアニメーションなどに利用する場合に、有料プランへの移行を考えればよいでしょう。

ここでは、まず無料で使えるWRTNのStable Diffusionを利用してスポーツカーのイメージを生成し、それを3Dデータ化してみることにしましょう。
Tripoでは、3D化する対象イメージに背景があると処理できないため、プロンプト内に「背景は白で」のような指示を含める必要があることに注意してください。
サンプルは、「白い背景で赤いスポーツカー」という単純なプロンプトで生成したものですが、フェラーリとマツダRX-8とテスラが融合したようなデザインになりました。

イメージが用意できたら、初期画面の下端の画像読み込みのアイコンをクリックして、イメージをドラッグ&ドロップするか、またはファイルのオープンダイアログから選択します。
有料プランでは、異なる角度からの複数のイメージを利用して3Dデータの精度を高められますが、シングルイメージからでも十分それらしい3Dデータを生成可能です。
イメージを読み込んだら、黄色い[Create]ボタンをクリックしてください。ただし、1回のクリックではファイル選択モードから抜けるだけで実際に押したことにはならないようなので、処理が始まらない場合には、もう1度クリックするようにします。

すると、処理の進捗度を示すバーが表示され、1〜2分後に、3Dのレンダリングイメージが表示されます。結果を見て満足できなければ、さらに25クレジットを使ってリトライ(再生成)も可能です。
その際には、「元のイメージに近いが、3Dのディテールのバリエーション違い」を生成する「Image-Aligned」か、「元のイメージとは多少違っても、立体としての構造を優先」して生成する「Structure-Aligned」を選択することができます。


3Dのレンダリングイメージをクリックすると、さらに編集・ダウンロードページに移行します。
たとえば、人物やフィギュアのデータの場合には、右上のRig & Animation機能で歩きや走り、ダイブのような動きをつけることもできますが、3Dプリント用データには無関係なので、Format(データ形式)からstlを選択してDownloadボタンのクリックで保存します。
あとは、お使いの3Dプリンタに応じて、純正またはオープンソースのスライサーアプリ(スライスしたように薄い層が積み重なった積層データに変換するため、スライサーと呼ばれます)で3Dプリンタが読める形式のG-codeに変換してプリントを行ってください。

絵文字からデジタル民芸品を作る
次に、絵文字から3Dプリントされた“デジタル民芸品”を作ってみましょう。
基本的に、どの絵文字でも3D化できますが、ここでは赤いクルマの絵文字を選びました。適当なアプリで絵文字を入力して、フォントサイズを大きめに設定し、スクリーンショットをとってトリミングします。
輪郭がボケて、やや解像感に欠けるイメージになったとしても、心配は要りません。Tripoは、元のイメージをあくまでもリファレンスとして使うだけなので、ある程度の解像度があれば大丈夫なのです。

これを先ほどど同じ手順で立体化してみると、側面のイメージだけから生成されたとは思えない3Dデータが見事に出来上がりました。
ダウンロードしたstlファイルをそのままスライスして3Dプリントすることもできますが、場合によって、ポリゴン数が多すぎて処理できない旨のメッセージが表示されるかもしれません。
そのようなときには、MeshLabのようなオープンソースの3Dエディタでポリゴン数を減らしてからプリントしますが、よほど極端に減らさない限り、今回のような3Dプリントのクオリティに大きな影響は見られません。



最終的に、3Dプリントされたものに、ポスターカラーマーカーでカラーリングを施しました。ゆるい感じの塗り分けですが、それも“デジタル民芸品”の味ではないかと思います。

埴輪や土偶も触れられるミニチュアに
最後に写真からの3D化の例も紹介しておきましょう。
ちょうど、上野にある東京国立博物館で特別展「はにわ」が開催されていて、ほとんどすべての埴輪や土偶が撮影可能だったので、挂甲の武人や馬の埴輪、遮光器土偶などの写真を撮ってきて、立体化してみました。
このような写真の背景を削除するには、iOS/iPadOSの写真アプリの被写体抽出機能を使うと便利です。
たとえば、写真内の埴輪本体にタッチしてそのまま少し待つと輪郭が光って抽出されたことを知らせます。
そこで指を離すとメニューが表示されるので、[共有]を選択して[画像を保存]を選べば、背景のない被写体のみが保存されるので、これをTripoに読み込ませるわけです。
最近ではスワニーのKidoodle MiniBox A1のように、子どもでも安全に利用できる3Dプリンタ製品も出てきていますので、冬休みに親子で家族やペットの写真からミニチュアを作ってみても面白いでしょう。
筆者もいろいろと試してみるつもりです。

おすすめの記事
著者プロフィール
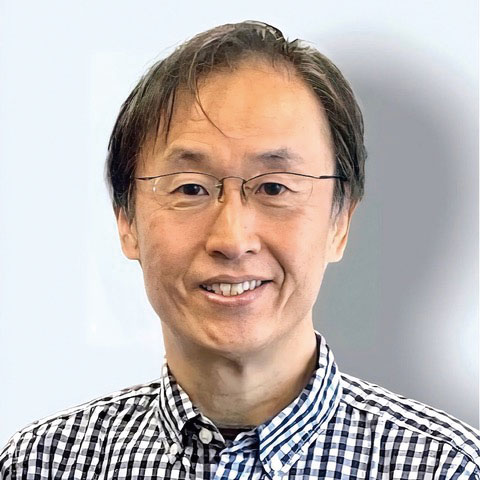
大谷和利
1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。










![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)