ナローベゼルによる画面最大化
2018年に誕生した「11インチiPad Pro」は、12.9インチモデルよりも気軽に持ち運ぶことができ、しかも、ナローベゼル化によって実質的なスクリーン面積が十分確保されているという意味で、筆者にとってジャストサイズの高性能iPadといえた。
発表当時、AppleはA12X Bionicを搭載したこのモデルが、市場の92%のノートPCよりも高速であるという表現で処理速度の速さをアピールしたが、使ってすぐにそれを実感できた。
このとき、iPhoneはXSシリーズが出たところで、こちらのデザインは縁に厚み方向の丸みがある形状だった。これに対して11インチiPad Proは側面を直角に切り落としたフォルムで、かつてのiPhone 4のデザイン手法を思わせた。この新たなデザインテーマは、その後のiPad AirやiPad(第10世代)に受け継がれ、iPhoneでも12で復活することになる。
また、本体背面に「Smart Connector」が設けられたことで、専用の「Smart Keyboard Folio(キーボード機能付きカバー)」を磁力でダイレクト、かつワンタッチで接続できるようになり、ワイヤレスキーボードにつきもののペアリングや電池残量などに煩わされずにタイピング可能となった。
そして、Apple Pencilも第2世代の、本体に磁力吸着してワイヤレス充電されるタイプが用意された。それらの複合的なメリットにより、筆者はノートMacの代わりにこのiPad Proを持ち歩く機会が増えていったのである。
Smart Keyboard Folioの賛否両論
Smart Keyboard Folioのキータッチについては賛否両論あったが、個人的にはさほど気にならず、むしろ図書館などの静謐さが求められるような場所でも、静かにタイピングできることは大きなメリットといえた。
また、キートップが密閉構造なので隙間に埃がたまらず、万が一、水などがかかってもメカ部分がダメージを受けることはない点は安心であった。
その一方で、iPad Proの角度が立て気味とやや寝かせた状態の2つしか選べないことは残念なポイントであり、たとえば旅客機のエコノミー席などの前後方向の余裕があまりない状態では不便を感じることが多かった。
この角度調整の問題は、2020年に「11インチiPad Pro(第2世代)」とともに発表された、ヒンジ機構を備えるバックライト付きの「Magic Keyboard」によって解決をみることになる。
筆者は、iPad本体を買い替えることなくMagic Keyboardのみを買い足し、より快適なモバイルワーク環境を得ることができた。反面、キータッチ改善のためにキーのメカニズムがより標準的なものになり、この部分の防水機能が失われたことは、やや残念に感じられた。
さらに、2021年にはiPad Proにも当時のMacBook Airなどと同じM1チップが搭載され、さらに性能が高められたが、筆者は今も初代の11インチモデルを使い続けている。それは5年前のモデルでも最新のiPadOS 17に対応し、今も記事執筆には十分以上の性能を発揮してくれるからなのだ。
著者プロフィール
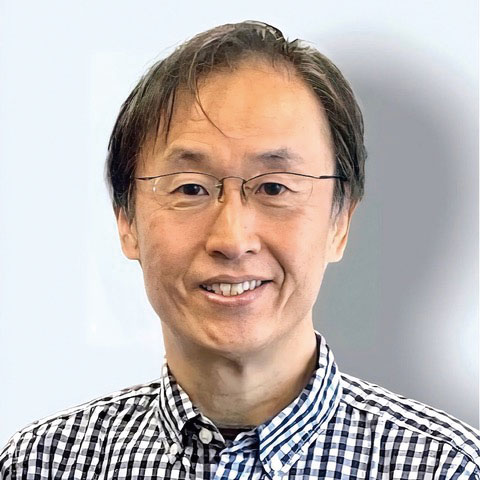
大谷和利
1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。




