会期も残すところ2週間を切り、駆け込み来場者が急増している「大阪・関西万博」。
中でも、映像だけに頼らず、その国や企業・団体を象徴する何かを実物で展示したり、人間によるリアルなパフォーマンスを取り入れたりして、その場に来なくては味わえない体験を提供しているパビリオンは、訪れておくべき価値があると感じる。
すでに読者の皆さんの中にも、足を運ばれた方が少なからずおられることと思うが、ここではテクノロジーの観点から4つのパビリオンを紹介し、会期末に向けた来場ガイドとしておきたい。
丸ごと森と化した館内を探検する住友館
今回の万博で筆者が訪れた中では、コンセプト、規模、実装、わかりやすさの点で、個人的にもっともバランスが取れていると感じたパビリオンが、住友グループが総力を結集して作り上げた(といってよいだろう)「住友館」だ。
万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」の具体的な項目のうちで、特に「いのちを知る」、「いのちを育む」、「いのちを守る」、「いのちを響き合わせる」に寄り添うコンセプトを強く反映した住友館は、まず外観が「住友の森」の所在地である愛媛県別子の山並みをイメージしている。

来館者が館内に入ると、1組に1つずつ「風の妖精が宿るランタン」を渡され、コンセプトムービーを観ながらミッションが与えられる。それは、「UNKNOWN FOREST」と呼ばれる森の、主のような存在だった大樹「マザーツリー」を復活させるために、各自がランタンに導かれるように森の中を旅していくというもの。そして、さまざまな動物や植物たちと出会い、その「いのちの物語」を集めてマザーツリーに還すことで大樹は復活し、次のステージへと進むことができる。
そのために、住友館の内部は丸ごと人工の森になっており、風の妖精に誘導されてランタンを置いたり木の枝にかけると、それまで隠れていた動物たちが顔を覗かせたり、姿を現したりする。それらは、さすがに本当の生き物ではなくレプリカだが、森のどのような場所に何が潜んでいるかを理解できるように工夫されている。


住友館のユニークさは、森の中で来場者が自由に歩き回れるところだ。他のパビリオンでは、一定人数のグループごとに3つほどに分かれたゾーンを順番に回ったり、グループ分けをせずに順路に沿って映像や写真、展示物を見て回るものが多い。これに対して住友館では、実際の森を探検しているかのような感覚を味わえる。
主宰者側にとっては、来館者の誘導や安全性の確保などに神経を使う、負担の多い見せ方だが、あえてそうする道を選んだことに拍手を送りたい。
総合プロデューサーは、2005年愛・地球博トヨタグループ館をはじめ、ミラノ万博やドバイ万博の日本館を手掛け、「リアルな価値体験の創造」をモットーにされている内藤純さんとのことで、大いに納得した。


マザーツリーにランタンを還した後は、シアターに移動して、UNKNOWN FORESTでの体験の伏線回収となる映像とパフォーマンスを鑑賞する。それは、背景の映像と前掲の透過映像の間で生身のダンサーが躍動的なダンスを披露するというスタイルで、リアルな立体感のある見せ方が特徴的だ。一般の来館者は撮影禁止の場所なので、SNSにもアップされることの少ないパートだが、これだけでもかなり見応えがある。

出口付近には、予約なしで自由に出入りできるエリアがあり、リトさんの葉っぱ切り絵作品の展示スペースのほか、住友グループの企業が誇る各種の技術や取り組みが、無数のボックスとして壁の両側を埋め尽くしている。
それだけのネタを集めてくるのも大変だったようだが、一つひとつ熱心に見る人もいて、筆者自身も住友グループの底力を知る良い機会となった。

なお、住友館は千本の木を伐採して建てられたのだが、従来の板材の加工法では少なからぬ端材が出てしまうため、原木を薄く桂剥きしたものを合板に加工することで、芯材のみが残るようにしている。その芯材も無駄なく活用してベンチや階段の部材に応用されているほか、万博の開催期間内に伐採した木の10倍にあたる1万本の植林を終える予定だ。一時期は、パビリオンの出口に近い軒先に燕が巣を作っていたこともあったそうで、自然に近いパビリオンならではのエピソードといえるだろう。
加えて住友館では、子どもたちを対象として「森のがっこう」で植林について学び、スギの苗木を植木鉢に植える約25分の植林体験イベントも1日4回行われている。住友館の外壁に並べらたそれらの植木鉢には、植林の大切さをアピールする役割もある。

ちなみに、こちらのWebサイトから、自宅のプリンタなどで印刷可能な住友館の公式リーフレットがダウンロードできる。同館ではこれを冒険マップと呼んでおり、万博に来られない方や、予約が取れない人も、その魅力の一端を知ることができるだろう。
二重の仕掛けで「自己とは何か」かを問うnull²
続いて紹介するのは、メディアアーティスト(ほか、肩書き多数の)落合陽一さんがプロデュースしたnull²(ヌルヌル)。周囲の風景を歪んで反射する、鏡面膜で覆われたキューブを組み合わせたパビリオンだ。

null²のテーマは、参加者に人間の自己認識や存在とは何かを問いかけることにある。“null”はプログラミング用語で「値がない状態」を指し、その何も定まっていない状態を「新たな価値が生まれる可能性の場」として捉え直す。そして、人から記号性を取り払い、他者との境界線を曖昧にしていくことで、そもそも生命とは?という根源的なことを考えさせるようになっている。
参加者は事前に自身の全身を「Scaniverse」というアプリを使って3Dスキャンし、Mirrored Body(null²公式アプリ)に転送して、趣味や性格、特技、声などと共に保存しておくことが求められ、そのデータが館内で展開されるインスタレーションの中で選択的に利用される仕組みだ。スキャンデータは必須ではなく、データを用意しても必ずしも選択されるとは限らないが、スキャンすることで体験をより完全なものにできる可能性が高まる。
館内の体験スペースも、床面、天井を含めて鏡面になっており、特に床を傷つけないように靴を脱いで内部に入る。
ダイアログモードでの体験は、Nullの森(コンピュータが自律的に生成した光のパターン=人工生命を鑑賞)、モノリスとの対話(人類史のタイムラインの振り返りとデジタルネイチャー時代への遷移)、AIアバターとの対話(選択されれば、自分でありながら自分ではないアバター=“null”が出現)、記号の解体儀式(アクチュエーターがミラーキューブを振って象徴的に自己の記号性解体を表現)からなり、全体で30分の長さがある。また、対話をなくして空間的な映像体験のみに絞り込んだインスタレーションモードもあり、こちらは10分で終了する。
しかし、どちらも予約が取りにくく、体験できずにガッカリして帰る人が多いことを残念に思った落合さんは、予約なしに45秒間で館内を通り抜けるウォークスルーモードを追加して、少なくとも館内の様子を味わえるようにしている。このあたりの経緯は、こちらで読むことができるが、null²実現の裏には、さまざまな苦労があったことが伺える。本来は、知らなくてもよい情報かもしれないが、知って体験すると、目にしているもの以上の感慨を抱くかもしれない。

実は、メインの体験の後にもう1つの仕掛けがあり、すでにブログやSNSでも書かれていたりするのだが、それはマジックの種明かしのように知らないほうが楽しめる種類のものなので、ここではあえて書かないことにした。写真が少ないのもそのためだが、住友館とは別の意味で考え抜かれ、驚きに満ちた構成のパビリオンであることは間違いない。
コミュニケーションの未来を垣間見せるNTTパビリオン
NTTのパビリオンのコンセプトは「PARALLEL TRAVEL」。それは、時空を超え、リアル空間とデジタル空間に存在する複数の現実を並行して行き来する世界の到来をイメージした言葉である。館内は、それぞれ「コミュニケーションの進化と普遍」、「時間空間の共有」、「存在を感じる」をテーマとする3つのゾーンから構成されている。
パビリオン自体は、テンション(張力)構造によって内部の柱を最小限に抑えた設計が特徴で、日本初の試みとして主要なテンション部材に直径9ミリのカーボンファイバーが用いられている。外周部は自由に通れる回廊になっており、霧を発生させて冷却効果を得ると共に、包み込まれるような雰囲気や、自然と建築の境界を曖昧にする効果を作り出す。
電電公社として未来のテレビ電話などを出展していたEXPO’70のときとは逆に、黒電話など過去の通信機器を振り返るところから始まるゾーン1には、大いに時の流れを感じた。


続くゾーン2では、先ごろ、年内での活動休止を発表したPerfumeの3人が、過去から未来へとタイムワープしながら歌い踊る様子を、ダイナミックな3D映像によって再現する。偏光メガネをかけて鑑賞するこのパフォーマンスは、その鮮やかさや臨場感から、その場で展開されているライブステージのように感じられる。しかし、通常ではありえないアングルからのカットを含めたダイナミックなカメラワークから、これが最新テクノロジーによって3D空間上に再構築されたパフォーマンスであることがわかる。
その背後にあるテクノロジーは、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network=革新的光無線ネットワーク)という、NTTが提唱する次世代の通信インフラだ。これは、光通信技術を基盤に、従来よりも大容量・低遅延・低消費電力のネットワークの実現を目指しており、空間情報をそのまま伝送することができる。
元々、この空間映像の制作にあたっては、EXPO’70で電気通信館があった吹田のステージでPerfumeがリアルなパフォーマンスを行い、複数設置されたLiDARや光学カメラ、マイク、メンバーそれぞれが装着した加速度センサー、位置トラッキングセンサーなどからの、その点群データ・映像・音響・振動などを取得。それらを高速光通信網で夢洲のNTTパビリオンに送ることで、計測から再構築までの時間差を最小化して再現したもので、今は、保存されたデータが再生されている形だ。筆者はライブ転送時の模様は観ていないものの、おそらく上演中のものは、それと寸分違わないはずである。
もし、このクオリティで他のライブも空間収録できるのであれば、Perfumeのファンは、活動休止中もそのパフォーマンスを十分楽しめるに違いない。


最後のゾーン3では、館内の3Dボディスキャナでスキャンされた来館者のデータを使い、デジタル変換されて変形する自分自身の姿と向き合う。null²にも通じるインスタレーションだが、全力でそこに振り切ったnull²とは違い、こちらは3つあるゾーンの中の1つという位置づけであり、存在意義を問われることなく、参加者全員が穏やかに自分のデジタルツインと向き合うことができる。

3つのドームで「海の蘇生」を学ぶBLUE OCEAN DOME
BLUE OCEAN DOMEは、NPO法人のZERI JAPANが出展している、滑らかにつながった3つのドームから構成されたパビリオンだ。ZERIは、Zero Emissions Research and Initiativeの略で、廃棄物ゼロ実現のために、資源やエネルギーの循環再利用を促進し、環境教育や普及啓発活動を通じて、企業や社会の意識・行動を変えることを目指している。
今ではドーム型の建築物自体は珍しくないが、BLUE OCEAN DOMEは、3つのドームのそれぞれが異なる工法によって作られているところが他とは大きく異なる。具体的には、直径約19メートルで「循環」がテーマのドームAは、曲げ加工された竹の集成材。直径約42メートルで「海洋」がテーマのドームBは、CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic=炭素繊維強化プラスチック)。直径約19メートルで「叡智」がテーマのドームCは、再生紙管と木材のジョイントの組み合わせによって、それぞれの骨組みが構成されている。全体設計を行った坂茂(ばん・しげる)さんは、紙管を用いた建築の第一人者でもある。

ドームAのテーマである「循環」は、降雨から海に至る水の道筋をモチーフとするインスタレーション作品で表されている。一定量の水が溜まると流れ出す金属の受け皿部分は、新幹線の先頭車両の外板を叩き出しによって成形している職人さんたちが手がけたもので、表面に撥水塗料が塗られており、流れ出した水が滑るように走っていく。その絶妙なバランスを実現するために、職人さんは現場で何度も面の修正を行なったそうだ。


CFRP製の骨組みを持つドームBには、直径10メートルの巨大なLEDスクリーンを使って、テーマである「海洋」の美しさと危機の両方をリアルに見せる映像が上映される。スクリーン自体が宙に浮かんだ地球のようでもあり、説得力を持って海洋汚染の深刻さを印象付けることに成功している。このスクリーンを覆うシェル部分もCFRP製である。
ちなみに、CFRPは製造時のエネルギー消費が鉄鋼やアルミよりも多く、リサイクルしにくい素材だが、軽量なために基礎工事の負荷が小さくて済み、会期後にモルディブに移設して利用するという高耐久・長寿命性のメリットから採用されたものだ。

「叡智」がテーマの3つ目のドームCは、海洋保全の最前線で活動する人や団体の取り組みを紹介するスペース。ワークショップ、講演、国際シンポジウムなどを行い、「海を守る知恵」を共有する知的体験の場でもある。
また、料理研究家の土井善晴さんが味の設計を行なった「海と山の超純水」が販売されており、熱中症対策として適度な塩分やミネラルを補給するうえで、ちょうどよい塩梅の飲料となっていた。

予約なしで見られるおすすめパビリオン
これら4つのパビリオンは、どれも素晴らしく、機会があればぜひ体験していただきたい内容を持っているが、それだけにとても予約が取りにくい状況も生まれている。
どうしても予約がとれず、それでも印象に残るパビリオンを見ておきたいという方に、おすすめしたいのが、予約なしでも入れるサウジアラビア館とカナダ館だ。
サウジアラビア館は、伝統的な都市構造を模した建物が、実際に同国の街や都市を探索しているかのような空間体験をもたらし、タイミングがあえば、中央の広場でプロジェクションマッピングとライブの楽器演奏や歌唱を組み合わせたショーを鑑賞することができる。
また、カナダ館は、なぜか取材許可が降りなかったのだが、グリップ付きホルダーに入ったiPadのAR機能を利用して、一人ひとりが館内の氷山の模型にかざすと、同国のさまざまな人々の生活が浮かび上がるユニークな展示を行なっている。
残りの会期はわずかだが、この記事が少しでも参考になれば幸いである。
著者プロフィール
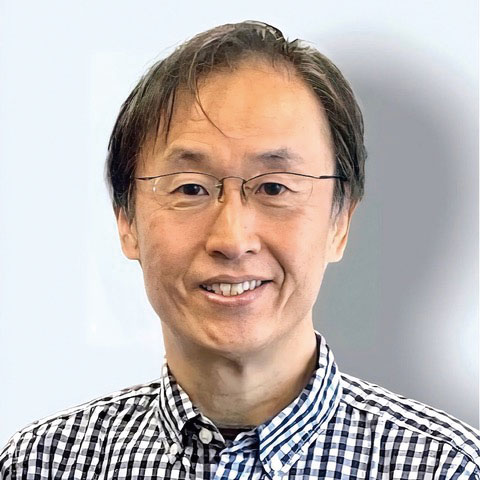
大谷和利
1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。




