※本記事は『Mac Fan』2022年12月号に掲載されたものです。
| IPC(Instructions Per Cycle) | big.LITTLE Processing | Alder Lake |
|---|---|---|
| クロックサイクルあたりの命令実行数のことで、プロセッサの性能指標の1つ。この十数年間はプロセッサの動作クロックの向上率が鈍化しており、IPCまたはプロセッサコア数を増やすことでシステム性能を向上させる手法が採られている。 | 2011年にARM社が発表したプロセッサの電力効率を向上させる仕組み。性能優先で設計されたCPUコアとエネルギー効率優先で設計されたCPUコアを組み合わせ、高性能と省電力を両立する。Cortex A15と同A7の組み合わせが最初のモデル。 | 2021年8月に発表されたIntel第12世代コアプロセッサでは、同社のメインストリーム向けCPUとしてははじめてヘテロジニアスマルチコアが採用された。高性能コア(Pコア)「Golden Cove」と高効率コア(Eコア)「Gracemont」で構成される。 |
省電力×高性能 AppleシリコンM1が実現した異次元の効率性
Mac初のAppleシリコン「M1」が登場したとき、従来のプロセッサを凌駕する高性能もさることながら、世界を驚かせたのはその圧倒的なエネルギー効率だった。M1は当時のモバイルプロセッサと比べて最大2倍の性能を持ち、モバイルプロセッサのピーク性能をわずか25%の消費電力で実現すると謳う。単なる高性能に留まらず、比類なき省電力性能をも実現する、その圧倒的な優位性はどのように導き出されたのだろうか。その答えは、iPhone向けのAppleシリコンである「A」シリーズに見出すことができる。

スマートフォン向けSoC(システムオンチップ)である「A」シリーズには、限られたバッテリ容量で長時間動作することと、他社製品に負けない高性能の発揮という相反するスペックが要求される。CPUの性能を向上させるには、動作クロックを上げると同時にIPC(クロックあたりの計算能力)を向上させる方法が採られるが、これらはいずれもバッテリ消費量と発熱量(内部温度)を引き上げる。またIPCを向上させるために多くの演算ユニットを搭載する高性能コアは、動作クロックを下げて消費電力を抑制することが難しく、バッテリ消費が激しい。
一方でCPUを低消費電力で動作させるには、演算ユニットをシンプルな構成にして(IPCを下げて)、トランジスタ数を最小限に抑え、動作クロックを大きく引き下げるのが効果的だ。さらに低電圧でも安定動作するトランジスタ構造を採用することで、コンパクトで省電力なCPUを実現できる。ただしこの省電力コアは、ピーク時でも高性能コアの数分の1程度の性能しか発揮できない。
2016年にAppleがiPhone 7に搭載したA10 Fusionは、高性能コア「Hurricane」2基と高効率コア「Zephyr」2基を搭載し、システムの負荷状況に応じて両者を「In-Kernel Switcher」という方法で切り替える。これによって、スタンバイ(待機)時には高性能コアを休止して消費電力を大幅に抑えながら、性能が求められる場合には高性能コアに動作をスイッチすることで最大性能を発揮する。

2種類のCPUコアを切り替えるのは、Appleが独自に設計した「パフォーマンスコントローラ」と呼ばれるコプロセッサの役目で、システムの負荷状況をリアルタイムで監視し、2種類のコアの切り替えと各コアの動作クロックや動作電圧をきめ細かく制御する。これはARM社が開発した「big.LITTTLE」という技術をベースにしたもので、「ヘテロジニアス(異種混合)マルチコア」と呼ばれる。同技術は、iPhoneだけでなくARMコアSoCを搭載するほとんどのスマートフォンに採用されている。
その中でもAppleシリコンの大きな特徴は、高性能コアのIPC(Instruction Per Clock)を大幅に強化している点だ。そのIPCはほかのスマートフォンに採用されているARMコアプロセッサを圧倒しているのはもちろん、同世代のIntelプロセッサすらも凌駕している。そのIntel社は昨年、第12世代コアプロセッサ「Alder Lake」でようやくメインストリーム向けプロセッサに異種混在コアを採用した。
進化する頭脳! A11 Bionicによる柔軟なコア制御
2017年にリリースされたiPhone 8/iPhone X用に開発されたA11 Bionicでは、パフォーマンスコントローラが第2世代へと進化し、より柔軟かつ高度なマルチコア制御が可能となった。A10 Fusionでは同時に動作するのはあくまで2コアであり、高性能コアと高効率コアをスイッチする方式だったが、A11 Bionicではもっとも低負荷での高効率コア1基のみの動作から、最大負荷時での高性能コア2基と高効率コア4基の計6コアフル稼働まで、さまざまコアの組み合わせで構成できるように改良された。これによってパワーレンジの幅がより拡大され、待機時の大幅な消費電力の削減と、フルパワー時の性能をより強化できるようになった。

この仕組みはもちろん、M1シリーズやM2にも受け継がれている。そのコア構成はAppleシリコンによって異なっており、iPadシリーズやMacBook向けのM1およびM2では高性能コア4基+高効率コア4基、上位のMacBook Pro向けのM1 ProおよびM1 Maxでは高性能コア8基+高効率コア2基となっており、上位モデル向けほど高性能コアの比率を大きくすることで高いピーク性能を引き出すようチューニングされている。
これら多数のコアの管理と制御を担っているのは、Mac用Appleシリコン向けに再設計されたパフォーマンスコントローラである。このコントローラの優れた柔軟性によって、M1 Maxを2チップ組み合わせたM1 Ultraの威力を最大限発揮させることが可能となっている。
異次元の省電力! Appleシリコンが描くヘテロジニアスマルチコアの未来
Appleシリコンは、高性能CPUコアと高効率CPUコアを組み合わせることで高性能と省電力を両立する異種混合コアのSoCだが、広い意味では、さらにまったく異なる演算ユニットを組み合わせることで、より高いエネルギー効率を実現するヘテロジニアスマルチコアのSoCである。その代表的なものがGPUコアで、AppleシリコンにはApple独自設計の演算ユニットが複数搭載されている。
GPUコアはさまざまなグラフィックス処理(画面描画)を担うのみならず、多数の演算コアを統合する高性能SIMD(Single Instruction, Multiple Data)プロセッサでもある。イメージや動画、音声などのフィルタ処理など、メディア処理能力においてCPUを大きく上回ることから、CPUからこれらの処理をオフロードすることで、より省電力でのメディア処理を実現する。

また顔認証や音声認識などに欠かせない機械学習を高速処理するNeural Engine、カメラからの画像をリアルタイムで処理し高画質化するイメージプロセッサ、動画や音声のCODEC(圧縮伸張)処理を担うメディアエンジン、プライバシー情報を保護管理するセキュリティコプロセッサ「Secure Enclave」などが搭載されている。
これら多くのプロセッサがそれぞれの得意分野を受け持つことで、システム全体としての機能や性能を向上させつつ、同時に非稼働プロセッサを積極的に休止させることで、高いエネルギー効率を実現しているのである。
おすすめの記事
著者プロフィール
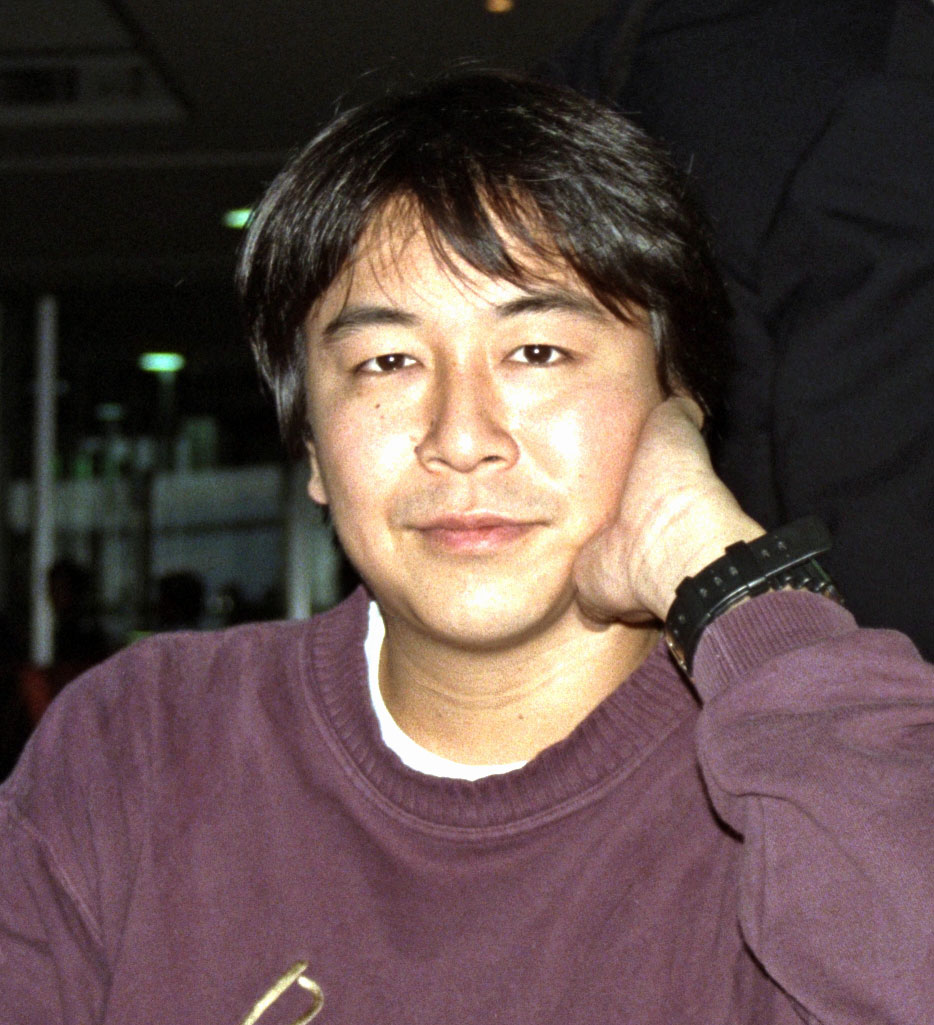





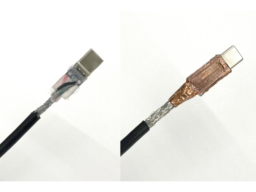




![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)