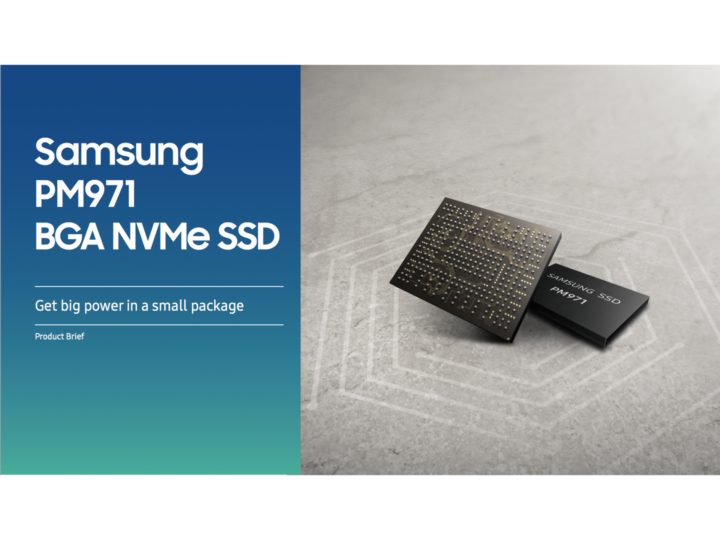※本記事は『Mac Fan』2017年7月号に掲載されたものです。
– 読む前に覚えておきたい用語-
| 不揮発性メモリ | フラッシュメモリ | フラッシュストレージ |
|---|---|---|
| コンピュータ用のメモリのうち、電源を切っても記録されたデータが失われない特性を持つものを指し、主にストレージや仮想記憶として使用される。大別して読み出し専用のマスクROMと電気的に書き込みが可能なEPROMがあり、3D NANDを含めてNANDフラッシュメモリもEPROMの一種。 | 不揮発性メモリの一種で、NAND型とNOR型に分類される。NAND型は構造がシンプルでNOR型に比べて高い記録密度が得られる反面、構造上データの上書きが不可能でブロック全体を消去してから書き込む必要がある。書き換え寿命が重視される用途ではNOR型が、大容量用途ではNAND型が用いられることが多い。 | NANDフラッシュメモリを記録媒体に用いたストレージデバイスの総称。メモリカードやUSBメモリ、SSDをはじめ、eMMCなどの基板実装型ストレージもある。iPhoneやiPadなどのスマートフォンやタブレット、MacBookに代表されるモバイルパソコンでは、フラッシュストレージが搭載されている。 |
NANDフラッシュメモリの構造とジレンマ
現在のiPhoneやiPadなどのiOSデバイスやMacなどのパソコンのストレージには、従来の磁気記録デバイスであるハードディスクに代わって、NANDフラッシュメモリを記録媒体に使った半導体ストレージが採用されている。
NANDフラッシュメモリはMacが誕生したのと同じ1984年に東芝によって開発され、2003年頃を境に爆発的にその普及が進んだ。当初はiPodなどのオーディオプレーヤへの採用から始まり、その後の大容量化と低価格化に伴って、スマートフォンやタブレットはもちろんのこと、最近ではパソコンのメインストレージの座をもハードディスクから奪いつつある。

NANDフラッシュメモリの大容量化は、主に製造プロセスの微細化によってもたらされてきたが、21世紀に入ってムーアの法則に基づいた半導体の進化に限界が見え始めた。これに加えてNANDフラッシュメモリは独特の構造が原因で微細化が難しくなっている。
NANDフラッシュメモリはその構造上、記録素子(セル)の中に設けたフローティングゲートと呼ばれる部分に電荷を蓄えることでデータを記録する。しかし、微細化が進むとこのフローティングゲート自体の容積が減少し、蓄えられる電化の量が少なくなることでデータの保持能力が低下する。
また、隣接するセルのフローティングゲート同士が接近することで、お互いに干渉が起きやすくなりエラーが増加する。保持能力の低下やエラーの増加に対しては、より強力なエラーリカバリー(ECCやLDPCなど)が必要になり、補正ビットの増加により実質的な記録容量が犠牲になるというジレンマがある。
このような状況を打破しさらなる大容量化を目指す手法として数年前から脚光を浴びているのが、高さ方向にセルを積層する3D構造のNANDフラッシュメモリ「3D NAND」だ。
3D NANDがもたらす制約の解放。一方課題は…?
従来のNANDフラッシュメモリはプレーナ型と呼ばれセルをX−Yの平面に配置する構造だが、3D−NANDはこれをX−Y−Zの三次元に立体的に配置し、プレーナ型では難しかったさらなる大容量化が実現可能だ。

3D NANDの特長は、製造プロセス自体を30〜50nmプロセスと低く抑えることでセル自体の特性を高く維持したまま、これを高さ方向に数十層重ねて配置することで記録容量を確保できることだ。
これによって製造プロセスの向上に伴うさまざまな性能上の制約から開放される。チップ全体のアクセス速度も2倍以上に向上し、さらにセル寿命も2〜10倍に改善される。
一方で3D NANDは従来のプレーナ型NANDとは製造方法が大きく異なるため、新たな設備投資が必要不可欠だ。さらに高さ方向に多層化したゲート層を垂直に貫通する細い穴を高精度にエッチングする高度な技術が必要であるため、現在はまだ歩留まりが低く製造コストが高い欠点を持つ。
それでもなお各社が3D NANDに注力するのは、今後大容量化競争に生き残っていくためには必要不可欠な技術であると認知されているためだ。
Samsungが先行する3D NAND開発
3D NANDの実用化で先行したのは韓Samsung社で、他社に先駆け「3D V−NAND」の名称で3D NANDを製品化した。
これを追う形で韓SK hynix陣営、米Intel&Micron陣営、東芝&Western Digital陣営の三陣営も3D NAND市場に参入し、現在ではNANDフラッシュメモリの大手4社が市場でしのぎを削る状況となっている。
現在、先行するSamsungはワンチップで512Gビット(64GB)製品を出荷しており、他の陣営も256Gビット(32GB)または384Gビット(48GB)の3D NAND製品を出荷している。一方でプレーナ型NAND製品ではいずれの陣営も128Gビット(16GB)の製品に留まっており、すでに3D NAND製品の容量がプレーナ型を大きく上回っている。
ただし、容量単価ではまだ3D NAND製品はプレーナ型NAND製品にまったく及ばないのが実情で、製造コストの削減と歩留まりの向上が今後の大きな課題となっている。
昨年、この3D NANDの特長を活かしたSSD製品がSamsungからいくつかリリースされた。1つはワンチップSSDと呼ばれるタイプの製品である「PM971 BGA NVMe SSD」。
BGAチップの中に4〜16枚の3D NANDとキャッシュ用のLPDDR4 SDRAM、NVMe SSDコントローラを統合し、ワンチップで最大512GBのNVMe SSDを実現している。インターフェイスはPCIe Gen・3の2レーン構成で、転送速度は最大1400MB/秒を実現するという。

また、HDD型のSSDタイプの製品「PM1633a SAS SSD」もリリースされている。3D NANDを積層した容量512GBの3D V−NANDチップを基板上に最大32個搭載し、16GBのSDRAMキャッシュも搭載する。
インターフェイスは12Gbps SASで、読み書きは最大1200MB/秒、容量は最大15/36TBのモデルが用意されている。主にエンタープライズ市場向けの2.5インチ15ミリ厚ドライブで、かつてない高速性と大容量をコンパクトなサイズで実現しているのが特長だ。

3D NAND市場を巡り、激化する企業間競争
Samsungは今年中には第4世代の512Gビット3D NANDを使用したより大容量の1TB BGA NVMe SSDや、32TB SAS SSDもリリースする予定で、SSDはいよいよHDDを越えた容量帯へとその進化を進めつつある。
他社もSamsungを追って開発競争を繰り広げており、3D NAND市場での覇権争いは現在進行形だ。そんな中、日本で唯一3D NANDを手がける東芝が、NANDフラッシュメモリ製造を含む半導体事業を分社化し、その事業を売却すると発表した。
ほかの事業での損失を穴埋めするための虎の子事業の売却だが、今年4月にはその入札にAppleが関心を持っていることが報じられた。東芝ではすでに512Gビットの3D NANDの開発を終えており、他社と充分戦える技術力と生産設備を持っている。
Appleの主要製品であるiPhoneやiPad、Macには大容量のNANDフラッシュメモリが多数搭載されており、有利な価格で大量かつ安定的に調達できればより大きな利益が見込めるためと推測される。次世代ストレージをめぐる企業間の争いは今後一層激しくなりそうだ。
著者プロフィール