
暑さの厳しい季節ということで、今回はぼくが10年近くかけて厳選してきた〝UL旅サンダル〟について。
写真はすべて、「ヨスミUL基準200グラム以下」という超軽量タイプなうえに、ちゃんと走れるアウトドア仕様。アウトドアの枠を越えて「街用アイテム」が主力となった大手のものから、エクストリームな用途のために開発された、海外ガレージブランドのものまで幅広く網羅している。
左から時計回りに解説したい。まず、一番左の5本指タイプの特殊な形状のものはビブラム社「ファイブ・フィンガーズSEEYA LS」。これは「ベアフットシューズ」という特殊形状のもので、サンダルというよりシューズだが、これは水際でも使え、速乾性も高かったので、ぼくの中ではサンダルカテゴリーに入れている。
ちなみに、ベアフットシューズというのは、近年注目を集めている「ベアフットランニング」のために開発された靴のこと。
一般的なランニングシューズに限らず、市販のほとんどの靴には、カカト部分が相対的に厚い、クッション性のあるソールが装着されている。それに対し、ベアフットシューズは、カカトから足先まですべてフラットで、わずか数ミリという薄いソールしか付いていない。ベアフットランを直訳すると「裸足で走る」だが、実際に裸足ではなく、「裸足に近い状態で走る」ということになるのだ。
400万年前にアウストラロピテクスが初めて直立二足歩行をしてから、「カカトの付いた靴」という履物が一般庶民に浸透する近代まで、人類はずっと裸足で生活をしてきた。その長い歴史によって、ぼくら現代人の骨格の構造は、実はまだ「裸足に適している」ということが、最近の研究で判明したのは有名な話。
つまり、通常の靴の構造は、人間にとっては不自然ということ。ベアフットシューズを履き始めの頃は、長年の習慣がたたり軽い筋肉痛になるが、いったん慣れると二度と元の靴には戻れなくなる。
衝撃の事実がある。ウルトラマラソンと呼ばれる100キロを超える過酷なレースの上位入賞者の半分近くが、今やベアフットなのだ。そういったレース参加者のほぼ全員が故障を抱えているが、ベアフットランナーには怪我が皆無という。そこまでやらなくても、軽いランニングや街歩きをベアフットにするだけで、内臓の位置や筋肉バランスが正常化し、姿勢が驚くほど良くなる。結果、体調が整い、疲れづらくなる。軽いうえ、機能的にも旅向きなのである。
次の茶色いのが、クロックス社「ウォーター・スイフター」。この中では、もっとも水に強いタイプ。その右が、イノヴェイト社「Recolite 190」。ベアフットラン用で、水際よりは陸で大活躍してくれる。これら2つの特徴は、カカトをつぶしてスリッパのように履けるため、機内や宿泊時にとても便利という点。最後のルナサンダル社「Venado MGT」は6ミリという極薄ソールに、ストラップだけという究極ミニマムな構造。これもベアフットラン用だ。
以上、日本未発売もあるので、販売方法などを知りたい方は、プロフィールにあるぼくのWEBメディアの「Favorite」ページに詳しくあるのでぜひ。
※この記事は『Mac Fan 2017年10月号』に掲載されたものです。
著者プロフィール

四角大輔
作家/森の生活者/環境保護アンバサダー。ニュージーランド湖畔の森でサステナブルな自給自足ライフを営み、場所・時間・お金に縛られず、組織や制度に依存しない生き方を構築。レコード会社プロデューサー時代に、10回のミリオンヒットを記録。Greenpeace JapanとFairtrade Japanの日本人初アンバサダー、環境省アンバサダーを務める。会員制コミュニティ〈LifestyleDesign.Camp〉主宰。ポッドキャスト〈noiseless world〉ナビゲーター。『超ミニマル・ライフ』『超ミニマル主義』『人生やらなくていいリスト』『自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと』『バックパッキング登山大全』など著書多数。


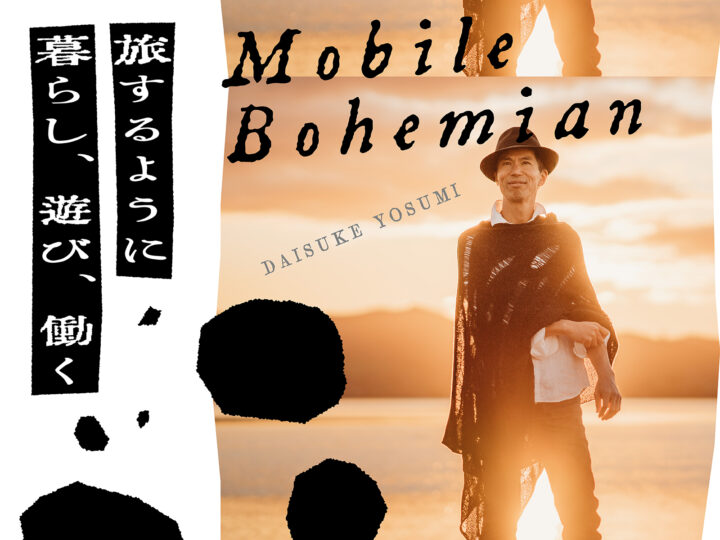



![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)