目次
- カメラマンが持っているのはiPhoneだけ。現代の映画づくりの“リアル”
- iPhoneカメラで追求した徹底的な「リアリティ」。あえて“手持ち”でワンカット撮影
- 撮影機材として用意された数十台のiPhone。バッテリとデータ管理に苦労も
- iPhoneカメラの映像は人の目に一番近い。歪みの補正が“味”につながる特性
- 撮影用アプリは「FiLMiC Pro」。iPhoneカメラの映像は、驚くほど多くのシーンで活用されている
- 「iPhoneで撮ってiPadで見る」。そのスタイルに感じる映画製作の未来
- 制作現場はApple製品だらけ。樋口監督が重宝するのは、iPad ProとApple Pencil
- 飽くなき映像への“欲望”。ARアプリとの連係など、iPhoneカメラの可能性はまだまだ広がる
カメラマンが持っているのはiPhoneだけ。現代の映画づくりの“リアル”
映画「シン・ゴジラ」の撮影において、さまざまなシーンに用いられたiPhoneカメラ。その特性を遺憾なく発揮したのが、東京湾アクアラインの中央に位置する「海ほたる」の海底トンネルが水没し、避難者が誘導されるショッキングなシーンの撮影だ。ここでは避難民が自分のiPhoneを使った実況動画をインターネットに投稿するなど、現在を象徴するような使われ方をしている。
このパートを担当したのは本編撮影をサポートするC班で、主に映画内に流れるニュース映像や本編の別アングルを撮影するのが本来の役割だ。そのC班の監督である石田雄介監督が撮影時の状況を語ってくれた。
「海底トンネルの断面は上下2層構造になっていて、上の車道は僕が率いるC班、キャストが登場する下の避難道では樋口監督がそれぞれiPhoneで撮影しました。撮影のために車道は1車線お借りして、車を10台以上並べてエキストラも何十人というかなり大規模な撮影だったのですが、カメラマンが持っているのはiPhoneだけという今の映画作りの“リアル”を象徴するような光景となりました」(石田)

2016年7月29日、全国東宝系にて公開
脚本・総監督:庵野秀明
監督・特技監督:樋口真嗣
准監督・特技統括:尾上克郎
出演:長谷川博己 竹野内豊 石原さとみ
©2016 TOHO CO.,LTD.
現代日本に初めてゴジラが現れたとき、日本人はどう立ち向かうのか?
iPhoneカメラで追求した徹底的な「リアリティ」。あえて“手持ち”でワンカット撮影
これまでiPhoneを映画の撮影現場に大量に投入するという事例はあまりなく、撮影を実施する前にはiPhoneカメラが描き出す「絵」の問題や「カメラワーク」など、かなりの試行錯誤があったそうだ。
「まず、テスト撮影で最初にびっくりしたのは、iPhoneで撮った映像が“きれいすぎる”ということです。これまでは携帯電話やスマートフォンで撮影した映像は画質が悪いというイメージがあり、本編で使ったカメラと比べると劣化している映像なのがわかりやく表現されることがあったのですが、iPhoneではそうもいきません。この映像がiPhoneで撮ったように見えるかな?という懸念は当初からあったのですが、樋口監督とも相談して、実際にiPhoneを使っている人はこの高画質を見慣れているのだから、そのまま使おうということになりました」(石田)
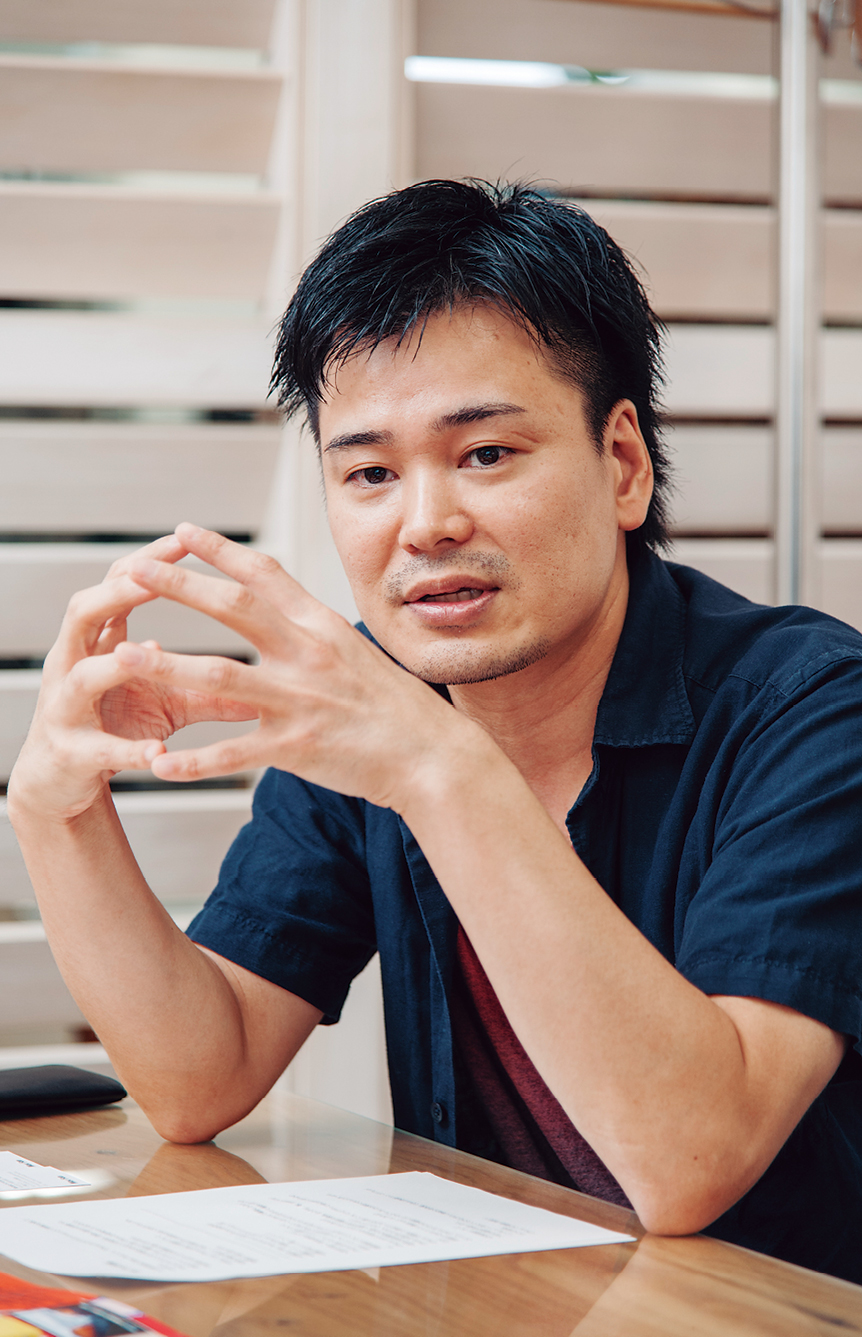
映像ディレクター。オフィスクレッシェンド所属。テレビドラマ、MVなどの演出・編集を務め、「モテキ」(2012年/大根仁監督)で第35回日本アカデミー賞優秀編集賞を受賞。翌年「ナオト・インティライミ冒険記 旅歌ダイアリー」(2013年)で劇場映画監督としてもデビュー。その他、嵐やAKB48などの映像作品も手がける。
一方のカメラワークについては、いかに一般人が撮ったように見せるかという演出が難しかったという。
「プロのカメラマンが撮ると、狙いを定めたAという地点からBという地点までのパン(※1)に無駄がないんですよ。普通の人はこの軌道に少し寄り道があるのですが、それを意識して揺らすとわざとらしくなってしまう。基本的に今は皆、動画を撮り慣れてますから、傾いて撮ったりとかわかりやすいミスはしないんですね。結局アタッチメントの機材なども使わずカメラマンが手持ちで普通にワンカットで撮ることにしました。なぜなら、そのほうが嘘のないリアリティを出せたからです。観客の人は日常で使い慣れたものについての嘘はすぐに見抜いてしまいますし、見抜かれたら白けてしまいます。そこのリアリティについては、とても大事にしました」
※1 カメラの向きを左右に振って撮影すること。
iPhoneには、カメラポジションの「不安定さ」や小ささを生かしたローアングルからの撮影、大胆な接写など、アクションカメラとはまた違った特徴があるとし、三脚やマウンタでの固定は特殊な目的を除き「iPhoneで撮影するメリットを損なう」ということで3人とも意見の一致を見た。
また、iPhoneカメラの構図に話が及ぶと、樋口真嗣監督は映像制作の視点では「縦構図」が今もっともアクチュアリティがあると持論を展開した。
「横長のスクリーンが前提の映画とはまったく親和性はないので今回の作品では使っていないんだけど、テレビの一般動画投稿を見てると縦動画って意外と多いでしょ、臨場感があるんだよね。だから、スマートフォンで見ることを前提としたメイキング動画などは縦にしたら面白いかもね(笑)」(樋口)

撮影機材として用意された数十台のiPhone。バッテリとデータ管理に苦労も
映画で使用されたiPhoneは、カメラマンが撮影に使う1台だけではない。
たとえば、劇中で陸上自衛隊隊員が10式戦車に乗車し、表情を回り込むように砲塔内で撮影されるシーンがあるが、ここでもiPhoneが用いられている。具体的には7台のiPhoneに加えて、4K撮影が可能なキヤノンの小型デジタルビデオカメラ「XC10」が即席のフレキシブルパイプにクランプ(※2)で取り付けられて、個別にカメラアングルを設定して同時に撮影が行われたという。上映されるのは10秒にも満たないカットではあるが、通常のカメラでは設置が難しい狭い砲塔内での映像を撮るために一切の手間を惜しまないプロの仕事に感嘆させられる。
※2 固定用の工具。
ほかにも日本に上陸するゴジラを眺める「野次馬」役のエキストラにも、数10台の実際に動作するiPhoneが小道具として配付されるなど、撮影現場では日々、撮影クルー用の機材を含めiPhoneやiPad、Macなど膨大な数のデバイスが運用された。映画の撮影自体は撮影部の管轄だが、撮影済みデータの管理を行うために「DIT(デジタルイメージングテクニシャン)」という専門の職種がいることを教えてくれたのは、VFXプロデューサーの大屋哲男氏だ。
「フイルムやテープの時代を経て、書き換え可能なデジタルメディアが映画撮影でも用いられるようになってから普及してきた職種で、撮影データの管理を専門に行っています。現場で映像ファイルをカメラからMacに安全にコピーして、エラーがないかチェックしたり映像にノイズが入っていないかどうか目視でチェックしたりというのが主な仕事ですが、まさかiPhoneでも必要になるとは思いませんでした。
映像を何カットも撮っていると128GBモデルでもすぐに容量がいっぱいになってしまいますが、iPhoneではメディアを入れ替えることができません。なので、あらかじめ満充電でデータが空のiPhoneを大量にトランクに詰めて、撮影済みのiPhoneと交換で手渡すのです。データのコピーと再充電はスタジオに戻ってからの作業ですが、なかなか大変です。データのコピーといっても大切な仕事なので、作業中はその場所の電源はほかのスタッフが使わないなどのルールを定めています」(大屋)

iPhoneカメラの映像は人の目に一番近い。歪みの補正が“味”につながる特性
iPhoneカメラで撮影した映像がリアリティを演出する点について優秀なのは、すでに見解は一致したが、さらに大屋氏はその要因が映像の「歪みのなさ」にあることを指摘した。もちろんカメラを左右に振った際に生じる映像の「ローリングシャッター歪み」についてはCMOSセンサ(※3)特有の現象として存在するが、比較的動きが少ない被写体については通常のカメラと遜色がないという。
※3 「Complementary Metal Oxide Semiconductor」の略称。日本語では、「相補型金属酸化膜半導体」などと訳される。レンズをとおして入ってきた光を電気信号に変える役割を果たす。
この点について樋口監督は「より厳密に言えば、iPhoneカメラのレンズには根本的な意味での歪みはあるんです。こんな薄いところのこんな小さな玉(レンズ)で映そうなんてのが本来は無理なんだけど、ソフト的に逆方向に歪ませて補正しているわけ。でもこれが見る人が見ると魅力的で“味”があっていいんですよ。これまでのスマホよりも画角は広いんだけど、魚眼レンズのように映像の中心が遠くに行ってしまうような歪みじゃない。中心の見せたいものは大きく映っているのに周辺の絵もきちんと映っているという、ものすごく変な特性があってね。これってもしかしたら人間の目の特性に一番近いってことかもしれないですね」と語った。

映画監督。「ゴジラ」(1984年/橋本幸治監督)のスタッフとして映画界デビューし、「ガメラ 大怪獣空中決戦」などで特撮監督を担当。「日本沈没」「のぼうの城」「進撃の巨人」2部作などで監督を務める。
また、この独特のiPhoneカメラの特性は、ほかのビデオカメラではとても再現が難しいという。
「ロケハン(※4)で『このアングルで撮りたい』って事前にiPhoneで撮るでしょう、ところが、あとで世界標準のアレクサ(※5)を持ってきて構えてもまったく同じようには撮れないんですよ。1日レンタルするだけで何台もiPhoneが買えるような高級業務機なのにですよ(笑)。これは今だから面白く話せるけど、いろいろ悩みの種になりましたねえ」(樋口)
※4 事前に撮影候補地に赴いて行う設定作業。
※5 デジタルシネマカメラのフラッグシップ機。
さらに大屋氏はiPhoneは映像の色味も優秀という。
「今はもうiPhoneもiPadも絵の見え方がマスモニ(※6)クラスなんですよね。そういう意味でも非常に優秀。でも、ほかのモニタで見るとそこまで色が良くないから、おそらく色温度の管理とかすべてのアップル製品はデバイスごとに厳密にチューニングされてるんですよね。なにせ元データよりもかなりきれいに再生されるんですから驚きです」(大屋)
※6 映像確認用のマスターモニタ。
撮影用アプリは「FiLMiC Pro」。iPhoneカメラの映像は、驚くほど多くのシーンで活用されている
iOSのソフト面に話が及び、本作では撮影前にiPhoneの撮影パートで使うアプリを統一していたことなども語られた。石田監督は当初は純正カメラアプリの利用を想定していたが、主にテクニカルな理由で「FiLMiC Pro」を利用するよう大屋氏が提案したという。
「カメラテストの段階からFiLMiC Proを使って撮影してもらったんです。というのも、このアプリは24p(※7)に対応しているのと、iPhoneカメラネイティブの解像度で撮れるんです。撮影の時期的に最初はiPhone 6プラスの3K、後半は6sプラスの4Kで撮っています。そうせずに標準の60pでそのまま撮影すると、映画のフォーマットではカクカク見えてしまったりするので調整に余計な作業が増えてしまうんです」(大屋)
※7 毎秒24コマのプログレッシブ撮影のこと。主に映画用に用いられる。
実際には最終的に24pと60p両方の映像が混ざってしまったと語る大屋氏。とはいえ調整が施されているので、普通の人が見てもほぼわからないレベルになっているそうだ。
その利便性の高さから、当初想定していたよりも多くのシーンの撮影で用いられたというiPhoneカメラ。
「実はびっくりするくらい多くのシーンをiPhoneだけで撮影しました。どのシーンがそうなのか、確認してみるのも面白いかもしれませんよ」(大屋)
ここでは代表的なシーンをいくつか紹介するが、それ以外の場面は、ぜひ劇場に足を運んで自らの目で確認してみてほしい。

「iPhoneで撮ってiPadで見る」。そのスタイルに感じる映画製作の未来
ここまで映画「シン・ゴジラ」本編の各シーンでiPhoneで撮影した映像が用いられたことを紹介したが、ただカメラとして便利という単純な話では終わらない。撮影現場にiPhoneが浸透したことで、映像制作のワークフローも劇的に変わりつつある。今後ますますiPhoneの活用シーンは増えていくはず、と石田監督は語る。
「iPhoneは、カメラマンもディレクターも、役割は違っても全員肌身離さず持っているものです。そんなデバイスが、プロ機材にも匹敵するような性能を持ち始めているのですから、それを使わない手はありません。10年以上前にAD(アシスタントディレクター)をやっていた頃は、ロケハンに行って来いと言われたらデジタルカメラとビデオカメラを借りてきて、さらに連絡用のガラケーも持って、現地で写真撮影とビデオ撮影をしていたんです。こんな大変なことがiPhoneだけでできるんですから、だいぶ楽になったと思いますよ」(石田)
大屋氏と樋口監督の両名も、ロケハンの位置情報確認にはiPhoneのGPSが大いに役立っている、と口を揃える。
「大阪に向かう新幹線の車窓から、『あの建物いいな』と思ったら間に合わなくてもいいからその場で写真を空撮りしておくんですよ。そして、あとから写真の位置情報でその建物について調べるんです。あの刑務所みたいな外観の学校カッコイイな~、これそのうち学園モノに使えるかもと思って調べたら、本物の刑務所でした、ってなこともありました(笑)」(樋口)
また、撮影後の映像の管理でも、iOSデバイスが大活躍している。大屋氏率いるピクチャエレメントでは、ラッシュ(※8)の管理をiPadで行えるクラウドベースのアプリ「PE RUSH!」を開発・使用している。
※8 撮影の各段階における試写映像のこと。デイリーとも呼ぶ。
「それこそ昔は、撮影所で1日1回撮影したフィルムを試写室で確認しなければならなかったんですが、これが「PE RUSH!」で完全にパーソナルベースで確認できるようになりましたね」(樋口)
「シン・ゴジラ」の撮影でも同アプリがフル活用され、各撮影チームが撮影した映像などすべてのデータをiPadで確認している。アプリ上でDIT、VFX、編集の担当者が映像にアクセスして、書き込みをしたりカットの指示を出すなど制作を同時進行できるのが特徴だ。クラウドで管理している映像データを、関係者限定のiPad上でストリーミング再生する仕組みのため、撮影途中の情報流出やデータの紛失が抑えられるようになったという。また、MDM(※9)としての機能も備えているので、万が一のときは遠隔でデータ消去も可能だという。
※9 「Mobile Device Management」の略称。モバイルデバイスを管理するためのツール。
制作現場はApple製品だらけ。樋口監督が重宝するのは、iPad ProとApple Pencil
ちなみに、最終的な映像の編集はMacプロなどを複数台配置し、編集ソフトに「Adobe Premiere Pro」を用いて行われたという。VFXを担当する制作会社のピクチャーエレメントと白組のほか、庵野秀明総監督が経営するアニメ制作スタジオのカラーの3拠点に編集室があり、それぞれの編集データはクラウドを介して同期している。
「具体的な作業の流れとしては、たとえば白組さんで合成したカットを入れ込んで調整すると、すぐにカラーの編集担当と監督がチェックしてつまむ(※10)んです。すると即座にデータが反映されて、こちら側は『あっ、そう切られたの…』ってなるわけです(笑)。以前はデータを編集室に持って行って、絵が足りないとか連絡していたのですが、そうしたやりとりが同時にできるようになりました。本来なら効率化しただけ編集にかかる期間も短くなるはずですが、実際はどんな監督であってもそうはなりません。時間の許す限り映像を触り続けてしまう、映画監督ってそういう人たちなんですよ(笑)」(大屋)
※10 映像の一部を取り除くこと。
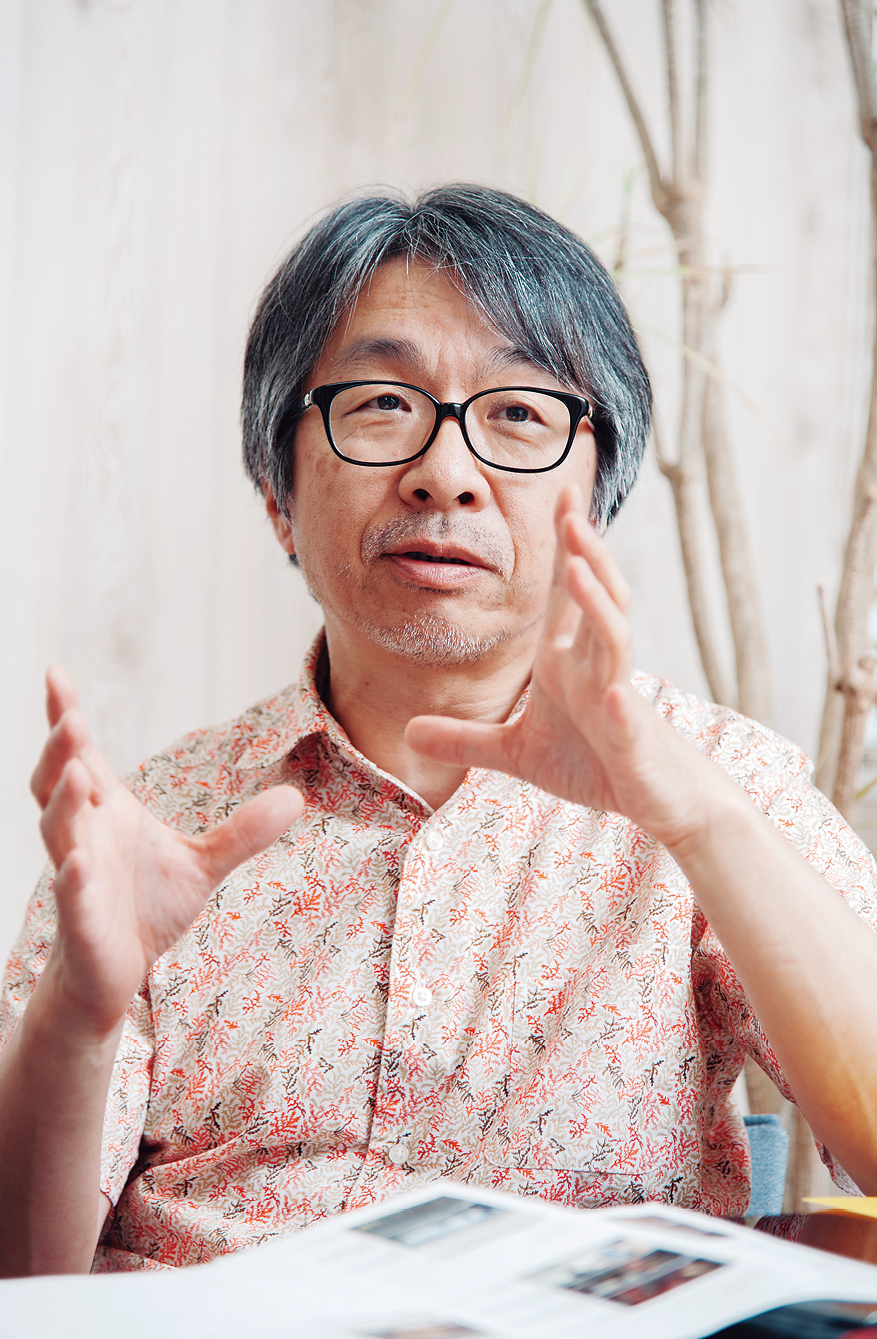
ピクチャーエレメント代表取締役。一般社団法人VFX-JAPAN理事。日本におけるVFXの第一人者として、映画やrテレビなど多くの映像作品でスーパーバイザー、プロデューサーを務める。
それでも編集履歴はすべてサーバに残るので、それを自分たちも把握できるようになったのはよいことだ、と大屋氏は言う。
以前から映像業界はMacが強いとされてきたが、さらに最近はApple製品ならどれを使ってもカラーマネジメントが統一されているので、それがMac以外のiOSデバイスの活用が進むポイントにもなっているという。
さらに、Apple製品の良さは「細かいところに手が届く」ことだと樋口監督は語る。
「今、一番重宝しているのがiPad ProとApple Pencilなんです。ラッシュに指示を書き込んだりするとき、今まで画面から手を浮かせて書いていたのが、今は普通のペンと同じ感覚で描けるからストレスがない。これまでサードパーティのタッチペンを買っては捨て、買っては捨てを5回くらい繰り返したけど、ようやく納得がいくものが出ました。遅いって(笑)。
ほかにもイメージを伝えるために紙に描いたものをiPhoneカメラでスキャンして補正したものをアップしてるんだけど…iOSはまだファイル管理がイマイチなところがあるんだよねえ。知らないところでファイルを上書きしたり消したり傍若無人なところがあって。こっちは仕事でやってるんだから『プロ』の名にふさわしい安定性が欲しいですね。…と文句ばっかり言ってますが、気がつけば30年以上もApple製品を使ってるんですよね(笑)」(樋口)
飽くなき映像への“欲望”。ARアプリとの連係など、iPhoneカメラの可能性はまだまだ広がる
今回の「シン・ゴジラ」では、一部ではあるがiPhoneカメラで撮影してiPadでラッシュを見るというスタイルを実践でき、「映像制作の未来を感じた」と石田監督は語る。また、カメラマンも野次馬役のエキストラもiPhoneを使っていて、どれがメインのカメラかわからないような面白い状況が生まれたが、これが役者をはじめ出演者の演技にも新たな影響を与えるのではないかと樋口監督は指摘する。
「映画でiPhoneを使うのは楽をしたいとか、そういう動機ではないんですよ。それは、飽くなき映像への“欲望”に、我々自身が対応せざるを得ないということへの、1つの解なんだと思います」(樋口)


おすすめの記事
著者プロフィール

栗原亮(Arkhē)
合同会社アルケー代表。1975年東京都日野市生まれ、日本大学大学院文学研究科修士課程修了(哲学)。 出版社勤務を経て、2002年よりフリーランスの編集者兼ライターとして活動を開始。 主にApple社のMac、iPhone、iPadに関する記事を各メディアで執筆。 本誌『Mac Fan』でも「MacBook裏メニュー」「Macの媚薬」などを連載中。











![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)