
イラスト/灯夢(デジタルノイズ)
「錆びた歌声のポップミュージックが響くライブハウスへ足を踏み入れると、待ち合わせていたゼベデ・コバキゼが「ジャンボ、こっちだ」と手招いた。席へ近寄るとスタッフがワゴンを押して現れ、メニューを出した。
「同じ物で」と英語で言って、ゼベデのテーブルに立つワイングラスを指さす。ジョージアの首都に立ち寄ったのだから名物の甘いワインを楽しみたい。
ワインをグラスに満たしたスタッフは手を開いて「5ラリ」と告げ、英語で続けた。「外貨なら1ユーロか1.25ドル。お好きな方で」
「ずいぶん違うな。1ユーロは2.5ラリだろう」
「いいよ。わたしが払う」
ゼベデがiPhoneを持った手を割り込むように差し出すと、スタッフはワゴンの下から決済端末のセンサーを引き出した。ゼベデは迷う風もなく1.25ドルと表示された画面を確認してTouchIDに指を置く。
「ごちそうになるよ。頼まれたMacは店のクロークに預けてきた。重くてね」
席についたおれはワインを啜り、去っていくワゴンにグラスを傾けた。
「旧ソ連邦でApplePayねえ」
「いつ経済が崩壊するか分からんからな。この店はテキサスに作った法人で決済してる。VPNを張っているんだよ」
「詳しいな」
「法人はおれが運営してるんだ──そんな顔するなよ。必死なんだ。どうやって国に依存しないようにするかいつも考えてる。君のクライアントもそうだ」
ゼベデはステージを指し、スクリーンに投影されているジョージア文字を〈ツヴィリ・カカ〉と読んでくれた。意味は二匹の猫。カカが猫、ツヴィリがペアを示すのだという。
「いまはライブハウスばかりだが、CDを百万枚売ったベテランなんだぜ」
「ペアの猫ねえ」
おれはステージを見なおした。曲調はわかりやすいが、ビッグバンドの素養を感じさせるアレンジだ。若く見えるがCDを売った時代にデビューしているなら四十代を越えているはずの女性歌手が一人スポットライトを浴びていた。彼女が遅れめに歌う錆びた歌声にベースが合わせ、バンドのグルーブがしっとりとついていく。猫の片方はこの女性歌手だろう。その他の楽器はカラオケだった。
もう一人はどこだ。若いベーシストが二十世紀に演奏していたはずはないし、譜面台に立てたiPadを忙(せわ)しなくめくるサックス吹きも違うはずだ。
そこでおれは気づいた。
「どうやってるんだ。歌手はリズムが取れてないぞ。ほら、また遅れた」
走る方に狂わないので気づきにくいが、明らかに歌手のリズムは悪い。ステージに立つベースやサックス吹きがついていけるのは分かるが、録音ではこんな不規則な揺れに対応できない。
「もう一人の猫がやってるんだ」
ゼベデは客席の後方へ頭を振った。
カウンターの脇に、欠けたリンゴのマークが輝いていた。Macbook Proの17インチモデルだ。
バックライトが男性を照らしていた。中央に向かって生える短い銀髪と黒いタートルネック、それに丸いメタルフレームと中近東の血を感じさせる鋭い顎が伝説のビジョナリーを思わせる。
「彼はコンラート・ドナウリ。歌ってるマデーの兄だ。本来は編曲やなんかに使うアプリケーションでリアルタイムで演奏してるんだと」
見られているのに気づいたか、コンラートはワゴンのハンドルに右手をかけて立ち上がり、青いLEDの輝くダイアルコントローラーを握ったままの左腕を振った──違う。義手だ。
ゼベデはおれの顔を見て言った。
「どんな国でも芸能は黒社会と結びつく。日本は違うのか?」
*
終演後、テーブルにやってきたコンラートは、おれに日本風のお辞儀をして、流暢な英語で言った。
「ジャンボさんですね。遠くまでありがとうございます」
「モノだけFedexで送るつもりだったんだけど、たまたま寄れる場所だったんだよ。CD、ありがとう」
コンラートは短冊形のカードを差し出して、裏のQRコードに指をあてた。
「僕らの曲はAppleMusicに入ってます」
「儲かってるかい?」
聞きはしたが答えは分かっている。ジョージアの曲など聴くユーザーはほとんどいない。よくて年に数十ドルだ。
コンラートは笑った。
「CDよりマシですよ。日本ではまだ買ってくれる人もいるらしいですね」
プレス業者に音源を納品した翌日には、Torrentにコピーがアップされているのだという。
コンラートは身の上を話してくれた。
ボーカルとベースのツインだった〈ツヴィリ・カカ〉だが、CDの売上がピークに達した二〇〇〇年頃、マデーがマフィアの怒りを買ってしまった。理由は話してくれなかったが麻薬か借金のどちらかだろう。話をつけにいったコンラートは腕を切られ、ベースが弾けなくなったため、DTM音源をリアルタイムで演奏することにしたのだという。
「妹──マデーは下手でね。録音にノっているように歌えないんです」
ゼベデが「こっちの猫が心臓部だったんだ」と言い添えると、コンラートは首を振った。
「いいえ。彼女の声質ですよ」
「どうしてMac? 高いだろうに」
「ジョージア語対応が無償ですから」
「なるほど」
Windowsも対応しているはずだが、追加インストールが必要なのだろう。なにも言わずに全部入れてくれるOSXはそんな誤解も味方につけている。
「で、ライブハウスでの収入が徐々に増えてきたところでまたマフィアに目をつけられた……」
コンラートが頷く。
「それで、国を出ると」
「ええ。全部を持って、今夜のバスで」
おれは暗い天井を見上げた。
テーブルの下にあるのは旧型のMac Proだった。幅20.6センチ、奥行き47.5センチ、高さは51センチもある。なによりも問題は重量だ。18キログラムの金属の塊は逃亡するミュージシャンにふさわしくない。
「参ったな。そんな理由を聞いてたなら別のマシンを持ってきたのに」
「いや、それでいいんです。僕はジョブス信者なんですよ。恰好を見れば分かるでしょう」
コンラートはタートルネックの折り返しを整えた。
「だから?」
「初代Mac、初代iMac、Power Mac G3にiBook。そしてこのMac Proの原型になったG5。彼の作るコンピューターにはどれもハンドルがついてる。ありがとう」
ラッシング用のタイをMac Proのハンドルに渡したコンラートは、肩を入れて立ち上がろうとしてよろめいた。
「──っと、さすがに重いな」
「やっぱり、無理じゃないか?」
それにハンドルは全部についていない。そう言いたくなったが、それを口にするのは憚られた。彼が信じて決めたのだ。誰がそれを止められるだろう。
妹を連れて店を出て行くコンラートは、扉を開けるときに肩を揺すってまっすぐに立って、足を踏み出した。
藤井太洋
2012年、セルフパブリッシングの『Gene Mapper』でデビュー。『オービタル・クラウド』で第35回日本SF大賞、第46回星雲賞日本長編部門を受賞。


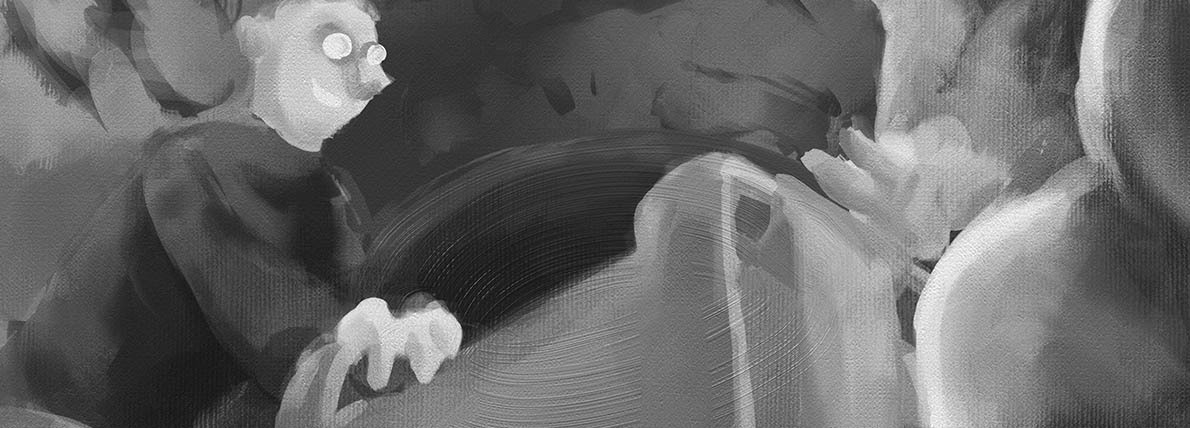



![フリーアナウンサー・松澤ネキがアプリ開発に挑戦![設計編]【Claris FileMaker選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/06/C5A1875_test-256x192.jpg)