2018年12月10日、インターネット商用化25周年&「ビッグ・デモ」50周年を記念したシンポジウム「IT25・50」が日本全国で同時開催された。伝説のコンピュータ科学者、アラン・ケイが基調講演を行うことで注目された本イベント。彼が語ったのは、テクノロジーの本来あるべき姿についてだった。
アラン・ケイという重要人物
2018年はインターネットが商用化してから25周年、また「ビッグ・デモ」と呼ばれるダグラス・エンゲルバートのNLS(oN Line System)デモが行われてから50周年にあたる。1968年、スタンフォード研究所で行われたこのビッグ・デモをきっかけに、今私たちが使っているデバイスにつながるIT革命が始まったのだ。
そんな節目の年を記念したシンポジウム「IT25・50」が、慶應義塾大学三田キャンパスを主会場に、日本全国で同時開催された。同シンポジウムは、あのアラン・ケイがライブ講演を行うということで注目を集めていた。
アラン・ケイは“パーソナルコンピュータの父”と呼ばれる、Macの曽祖父のような存在だ。ケイは、50年前のビッグ・デモを見て衝撃を受け、未来のデバイス「ダイナブック」を構想した。詳しくはケイ自身の論文「A Personal Computer for Children of All Ages」(あらゆる世代の子どものたちのためのパーソナルコンピュータ)を読んでもらうのが一番だが、ダイナブックとは、簡単に言えば今日のiPadのようなタブレット型コンピュータである。論文を発表した1972年にこれを構想していたのは驚くべきことだ。
ケイのダイナブックが画期的だったのは、単なる「未来科学者の妄想」に留まっていない点だった。ケイはこのダイナブックをまず学校に導入するべきだとして、米国の標準的な家庭で支出される文房具代や教科書代を調査。そこから、ダイナブックの価格を500ドル程度に設定し、その範囲内で利用可能な部品を用いて設計を行った。
さらに、ケイはダイナブックのOS開発も進めた。この研究は、ケイが当時所属していたゼロックス社・パロアルト研究所で行われ、自作のコンピュータ上で開発。試作マシンは「アルト(Alto)」または「暫定ダイナブック」と呼ばれ、画面上のアイコンをマウスを使って操作するグラフィカルインターフェイスを持つ、画期的なマシンだった。
その後、1979年11月から12月にかけて、アップルのスティーブ・ジョブズはエンジニアたちを引き連れてパロアルト研究所を訪問し、このアルトを見学。開発中のLisa(後のMacintosh)に大きな影響を与えたことは、シリコンバレーの神話の1つにもなっている。
未来のあるべき姿をつくる
今回のケイの基調講演は、ビッグ・デモ以来の50年を振り返るものだった。その中でケイは、「この50年でさまざまなデバイスが誕生したが、それらは“人間の知性を増強する”という1つの目的に向かって発明されてきた」と語った。NLSも、ダイナブックも、そしてアップルのプロダクツも、実は同じ未来に向かって、今手に入るテクノロジーをデバイスの形で表現してきたにすぎないのだ。
ケイは、「この講演の目的は皆さんにある論文を読んでもらうことです」と言った。その論文とは、ビッグ・デモを行ったエンゲルバートが1962年に発表した「Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework」(人間の知性の増強:概念的枠組み)だ。エンゲルバートはこの論文で、NLSでは実現できなかったさまざまな人間の知性を増強するアイデアを論じている。
ケイのもっとも有名な言葉に「The best way to predict the future is to invent it」(未来を予測する一番いい方法は、自らそれを創ることだ)というものがある。エンゲルバートもケイもジョブズも、未来を予測してそれに合わせたマシンを開発したのではない。未来はこうあるべきだと考え、自分で未来をつくろうとした。
エンゲルバートやケイの論文は、ネットで簡単にPDFを見つけることができる。ぜひ時間をつくって読んでみてほしい。「今のこと」が書いてあるし、「今まだ実現できていないこと」も書いてある。未来をつくる仕事の続きは、今を生きる私たちに託されているのだ。



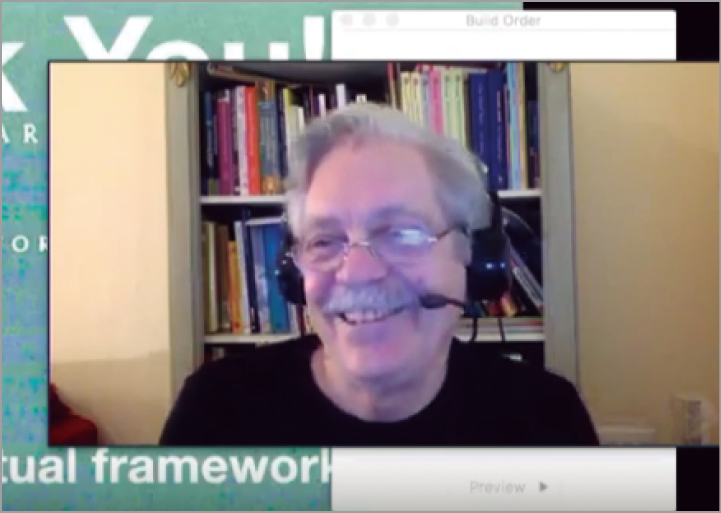





![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)