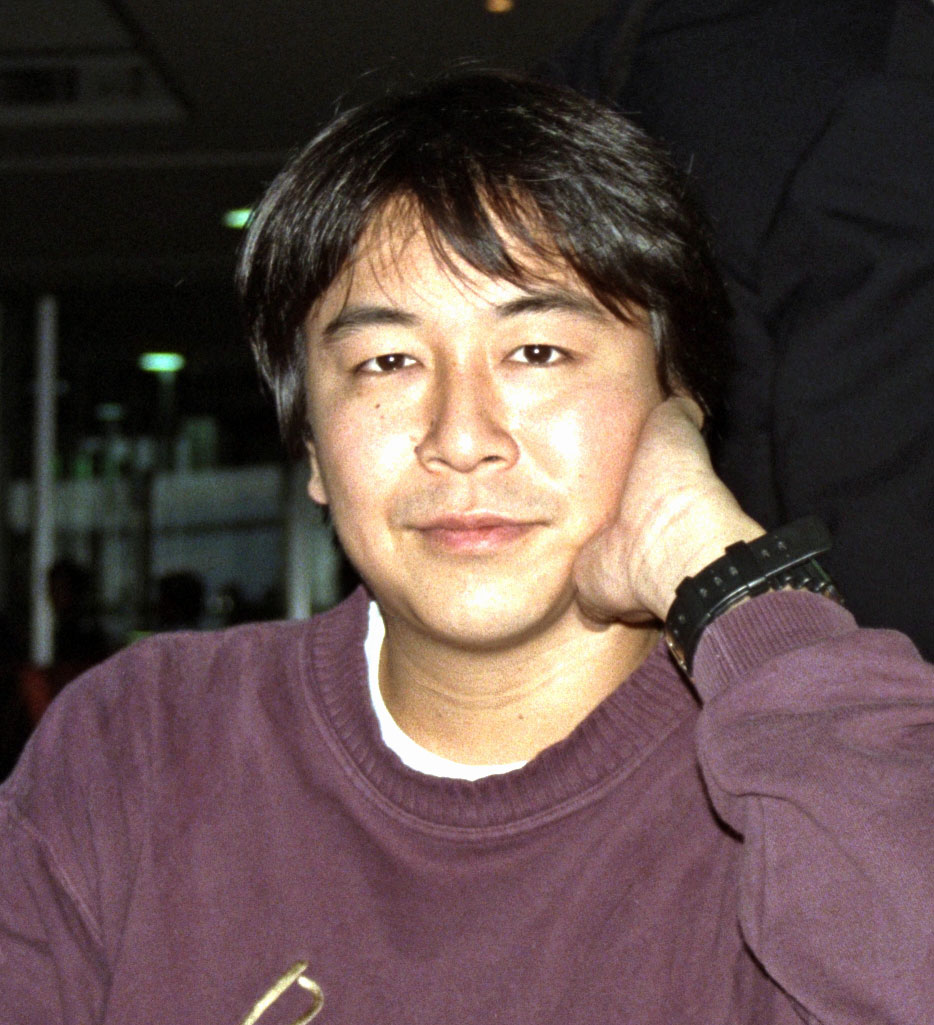Macintoshの実用性を飛躍的に高め、本格普及の狼煙を上げた名機「Macintosh Plus」。その誕生の経緯については別記事「Macが本格的に普及する転機となった『Macintosh Plus」の登場』」で詳しく解説したが、今回は視点を変え、その筐体の中に隠された「技術的な工夫」に焦点を当てる。
Macintosh Plusロジックボードの基本アーキテクチャと主要LSI
Macintosh Plusのロジックボード設計は、基本的には前モデルであるMacintosh 128K/512Kの設計をベースとしているが、そこに拡張性を加えつつ部品点数を削減するための工夫が凝らされている。そこでまずはMacintosh Plusのロジックボードアーキテクチャを見てみよう。

まずはMacintosh Plusを構成している5つのLSI(大規模集積回路) について説明しよう。

Motorola MC68000 CPU
MC68000はMotorolaが1979年にリリースしたCPU(マイクロプロセッサ)で、3.5μmプロセスで製造されていた。外部バスこそ16ビット構成ながら、内部では32ビットアーキテクチャを備えた当時としては画期的なプロセッサだった。そのアルゴリズムはシンプルかつ非常に洗練されており、パソコン用というよりは当時のスパコン用に近い設計になっていた。
当時MC68000を採用していたコンピュータとしては、Sun Microsystemsのワークステーション「Sun-1」、Commodoreの「Amiga 500」、そして日本ではSHARPの「X68000」シリーズなどが有名だ。
Zilog Z8530 SCC
Z8530 SCCはZ80 CPUで有名なZilogが開発した2チャンネルの高機能シリアルインターフェイスチップで、Macintosh Plusではこれをモデムポートおよびプリンタポートの制御のほか、次に述べる6522 VIAと組み合わせてマウスやキーボードとの通信にも利用していた。同期/非同期通信をサポートし、さらに最大230.4Kbpsという高速性を活かしてLocalTalkと呼ばれるローカルネットワーク接続にまで発展している。
MOS Technology 6522 VIA
6522 VIAは、Apple IIに採用されたCPU 6502向けに設計された多機能I/O(Input/Output)LSIで、2チャンネルの8ビットパラレルポート、16ビットタイマ&カウンター、シフトレジスタで構成される。このうちMacintosh PlusではパラレルポートのCh1をキーボードおよびマウスとの通信に、Ch2をFDD制御とサウンド出力などに使っている。タイマはサウンド(PWM)制御とインターバル割り込み、シリアルポートのボーレートジェネレータなどに使われている。
NCR 5380 SCSI
NCRの5380はMacに初めて採用されたSCSIコントローラで、初期のSCSI規格であるSCSI-1をサポートする最初のLSIである。ただしこの時代のSCSIコントローラはDMA(Direct Memory Access)機能を備えておらずPIO動作となっており、その後のMacに比べるとCPUに負荷がかかる設計だった。
それでもMacintosh PlusへのSCSIインターフェイスの採用によって、さまざまな周辺機器が接続できるようになり、Macの用途を拡大するうえで重要な立役者だったことは疑う余地がない。
Apple IWM FDC
IWMはApple IIシリーズ向けの外付けFDD(フロッピーディスクドライブ)「DISK-II」のコントロール回路をワンチップ化したLSIで、IWMはDISK-IIディスクコントローラの設計者であるスティーブ・ウォズニアックを指す「Integrated Woz Machine」の略だとされている。
AppleオリジナルのGCR(Group Coded Recording)エンコードに対応し、さらに一般的なFDDがディスクを定速回転させていたのに対して、モーターの回転数を可変とすることでディスク上の記録容量を向上させていた(720KBの2DD FDに800KBを記録できた)。
シンプルながらも工夫の凝らされたMacintosh Plusのロジックボード設計
Macintosh Plusでは、LSI以外のほとんどの回路は汎用ロジックであるTTL(Transistor Transistor Logic)とPAL(Programmable Array Logic)で構成されている。この当時はまだカスタムチップ(ゲートアレイ)の普及前だったこともあり、部品点数(TTLの数)を減らす目的でPALが多用されていた(Macintosh SEや同 IIにはゲートアレイが使われている)。
PALは設計者が簡単な論理回路をプログラムできるチップで、うまく設計することで複数個分のTTLの機能を統合することもできた。Macintosh Plusにはざっと見たところ7個のPALが採用されており、これによって部品点数を削減し基板を小型化していた。

Macintosh Plusは512×342ピクセルのモノクロビットマップのディスプレイを備えているが、そのビデオメモリはメインメモリの一部(約22KB)が割り当てられている。そのためCPUがメインメモリにアクセスするタイミングと、ビデオ回路がディスプレイ表示のためにメインメモリにアクセスするタイミングを最適化する必要がある。この複雑なタイミング制御の大半は、前述したPALによって制御されている。
メインメモリへのCPUとディスプレイ表示のメモリアクセスを調停制御するために、Macintosh Plusではサイクルスチールと呼ばれる相互アクセス方式が採用されている。これはメモリのアクセスサイクルを2分割し、CPUとディスプレイ回路へのアクセスを交互に行う方式で、CPUとディスプレイ表示の同期を実現するためにCPUは最大スペックの8MHzではなく、7.83MHzで動作していた。しかもディスプレイ表示のための周期的なアクセスを利用して、DRAMのリフレッシュサイクルを不要とする設計になっている。

次回はロジックボード以外のコンポーネントを見てみよう。
おすすめの記事
著者プロフィール