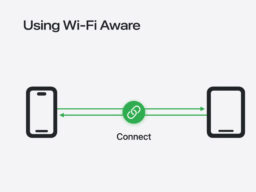すっきりとした薄さ、シンプルなデザイン。軽くて、でもパフォーマンスは一線級。iPhone Airは、実にAppleらしいモデルだ。
2025年9月19日に発売されるiPhone Airをひと足先に試用することができたので、その体験をお伝えしよう。
手で持っても、ポケットに入れても、とにかく薄いiPhone Air
iPhone Airは、写真で見ると飛び出したカメラ部分が目立ち、そこについてコメントする人が多い。しかし実際に手にすると、とにかく薄さが際立つ。歴代のiPhoneの中でもっとも薄く、同時に発売されるiPhone 17 Proの最薄部が8.75mmなのに対し、iPhone Airの最薄部は5.65mmと、3mm以上スリムな設計だ。

薄いだけでなく、軽く、しかも大きなディスプレイを備えているのが印象的だ。薄さばかりが話題になるが、ディスプレイは6.5インチと、従来のiPhoneのPlusモデルとスタンダードモデルの中間ぐらいの大きさ。さらに、重さは165gとスタンダードモデルよりも軽い。まるでディスプレイだけを持っているような感覚だ。

「最薄部」でスリムさを語ることに否定的だったり、カメラ部分の厚みについて揶揄したりする声もあるが、実際にiPhoneを使うときを考えてほしい。カメラ部分には基本的に手が触れないため、最薄部のスリムさは重要だ。使用感にダイレクトに影響する。
カメラ部分に“すべて”集約。iPhone Airのまったく新しいアーキテクチャ
カメラ部分の厚みについても、明確な理由がある。実はこのiPhone Air、歴代のiPhoneとはまったく違う構造を採用しているのだ。
初期のiPhoneからiPhone 16にいたるスタンダードモデル(iPhone 17の内部構造はまだ未公開)は、単セルのパウチされたバッテリを内蔵しており、iPhone XからiPhone 15 Proに続くProのラインナップは2セルのバッテリをL字形につないだ構造を採用している。これはチップセットなどを搭載したメイン基板と、3連のカメラのスペースを確保するためだ。
対して、iPhone Airは第3のアーキテクチャと言える構造を持っている。金属シェルに入ったバッテリは自由度の高い形状を持ち、薄い部分の全体を占有。そしてA19 Proチップや、カメラ、Face IDなどの主な内部パーツは、すべて“出っ張り”部分に詰め込まれた。言わば、“出っ張り”こそがiPhone Airの本体なのだ。

タフさの理由は“曲がっても戻る設計”。60kgfの荷重テストをクリア
この構造は、“薄いのに強い”iPhone Airの構造にも貢献している。
筆者は、iPhone発表会時にApple Parkで行われたブリーフィングで、iPhoneの耐久性テストに使われている機材を見せてもらった。そこで行われたのは、iPhone Airに60kgfもの荷重をかけるデモンストレーションだ。
まず、スマホの形を模した測定器を手渡され、「曲げてみて」と指示された。下図のように渾身の力を込めて曲げようとしたが、計測結果は30kgfぐらいだった。

その後のデモで、iPhone Airにはその2倍の力がかけられた。60kgfもの荷重がかかると、さすがにiPhone Airは大きくたわむ。しかし、力をかけるのを止めるとiPhone Airは元通りまっすぐに戻った。定盤の上に置いても、ガラス面はピッタリと平面のママだ。
史上もっとも強いiPhone Air。フレームもガラスもバッテリもすべてしなやか
この“曲げても戻る設計”がiPhone Airの特徴だろう。そのために、iPhone Airにはチタニウムフレームが使われている。従来のiPhone 16などに使われてきたアルミニウムフレームは、なかなか曲がらない一方、一度曲がったら元のカタチには戻らなくなってしまう。その点、チタニウムフレームはしなやかに曲がり、元に戻るわけだ。
もちろん、背面のCeramic Shieldと、タッチパネルのCeramic Shield 2も強度に貢献している。これらのガラスが割れず、しなやかに曲がって元に戻るのも驚きだ。また、先に述べた金属シェルのバッテリも、この曲げに耐える構造になっているとか。
iPhone 6/6 Plusでは、ズボンのお尻のポケットに入れて大きな荷重がかかると曲がって戻らなくなってしまう「ベンドゲート」という問題があった。しかし、iPhone Airはチタンのしなやかさを持って、より薄く、かつ強靭なボディを作ることに成功したのだ(AppleはiPhone史上もっとも強いと謳っている)。
1枚のガラスを削り出して作られる、iPhone Airの美しい背面。ただし“熱”には懸念も
背面ガラスにも注目したい。
カメラに向かって盛り上がっているように見えるが、それは正確な表現ではない。実はこの背面のガラスパーツ、厚いガラスを薄く削って作られている。つまり、カメラ部分が盛り上がっているのではなく、ほかが削られているのだ。
斜めになっている部分を見れば、この膨らみが別体のパーツで作られているわけではないことがわかると思う。部品を張り合わせて作っても、見た目に大きな差は出ないかもしれない。それでも“ガラスを削る”という時間のかかる作業工程を折り込むことで、この美しさが実現しているのだ。

搭載しているチップセットはフラッグシップのiPhone 17 Proシリーズと同じA19 Pro。今のところベンチマークを取ることはできないが、間違いなく歴代iPhone最強のチップセットだ。
ただし、冷却性能にこだわったiPhone 17 Proシリーズと違って、iPhone Airの冷却の仕組みは従来と同じ。熱伝導率がアルミニウムの1/10しかないチタンフレームなので、3Dゲームなど高負荷の作業を長時間続けると熱を持ち、処理速度が抑制されるはずだ。
対応するのはeSIMのみ。物理SIMのユーザは、買い替え前に確認を
先鋭的なコンセプトの製品だけに、ほかにもいくつか注意点がある。
まず、eSIM専用機でSIMトレーがないということ。iPhone Airは薄型化のためSIMトレーを持つ仕様はなく、日本も例外ではない。そのため、使用するためにはeSIMを用意する必要がある。

eSIMの利用に慣れている人にとって、この仕様はなんでもないことだが、eSIMをはじめて使うなら、お使いのキャリアで、どうやって物理SIM→eSIMに切り替えるか早いうちに調べておいたほうがいい。
ドコモやau、ソフトバンクなどのメジャーキャリアなら「eSIM転送」などの仕組みが用意されているが、MVNOだと少し手間がかかることもある。また、窓口で作業を依頼すると手数料(おおよそ2〜3000円)が発生するようだ。
カメラ、バッテリ容量、スピーカ性能ほか課題も明確。ただ、“Appleの挑戦”に胸おどる
また、カメラはデュアルフュージョンではあるが単眼なので、光学ズームは1~2倍のみ。便利な超広角はない。さらに、バッテリ容量もほかの新iPhoneと比べると限られている。

ほかにも、スピーカがモノラルだとか、USB-Cポートの転送速度が遅いとか(USB 2なので480Mbps)、DisplayPort Alt Modeが非対応とか、いくつか懸念点はある。たとえばXREALシリーズのような、サングラス型のディスプレイも使用できないということは覚えておきたい。
それら多少の欠点に目をつむれば、iPhone AirはAppleによる久々の実験的で、先鋭的なモデルである。その“尖り”を魅力に感じるのであれば、ぜひ購入を検討いただきたい。

おすすめの記事
著者プロフィール

村上タクタ
Webメディア編集長兼フリーライター。出版社に30年以上勤め、バイク、ラジコン飛行機、海水魚とサンゴ飼育…と、600冊以上の本を編集。2010年にテック系メディア「ThunderVolt」を創刊。