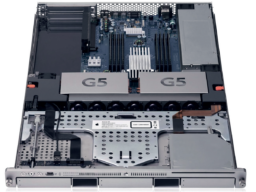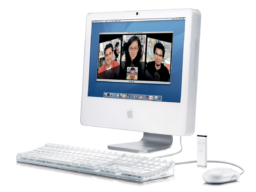There’s something in the air.はどういうニュアンス?
初代MacBook Airは、2008年1月開催のMacworld Expoのキーノートでデビューした。
発表に先立って、Appleは会場内に“There’s something in the air.”と書かれた垂れ幕を掲げていた。直訳すれば「空中に何かがある」だが、実際には「何かの気配がする」、「何かが起こりそうだ」、あるいは場合によっては「怪しい動きがある」といったニュアンスで使われる成句だ。
このイベントのキーノートでは、毎回、何らかの新製品が発表されていたことや、その時点では、製品名がわからなかったこともあり、この垂れ幕も「何かが発表されます」程度に受け取った人が多かったように思う。しかし、実際の発表が行われると、製品名のAirとかけた秀逸なコピーだったことがわかった。また、製品名の表記も、今と違って、MacBook Airの“Air”の線だけを細くするという凝りようで、Appleの力の入れようが窺えた。
最高のコンセプトと凡庸な性能
今では、ある種の伝説となった感もあるが、初代MacBook Airのお披露目は、スティーブ・ジョブズがアメリカではおなじみの黄色いビジネス封筒の中から取り出す演出とともに行われ、その薄さや軽さを視覚的に印象づけるものだった。
第2世代モデル以降は、サイドの造形がより明確にウェッジシェイプを強調するものとなり、I/Oポート類も剥き出しとなったが、初代モデルは4辺とも上面と下面から縁に向かって緩やかにカーブする造形によって、極限まで薄く見えるように意図されていた。
その流面体的なフォルムを完璧なものとするために採用されたのが、本体の右奥下面に設けられた格納式のI/Oポートだ。これは単なるポートカバーではなく、USB、Micro-DVI、イヤフォンの3つのポートを収めたユニットが、ヒンジ機構で出し入れされるというもの。格納時には、筐体の曲面の中に溶け込み、滑らかな外観となる。
製品の位置づけは、現在と違うプレミアムモデルの扱いで、価格も標準構成で22万9800円(税込)と、円安で高くなったといわれるM2搭載MacBook Airよりもはるかに高価だった。その理由の1つと考えられるのは、Appleがはじめて試みたユニボディ構造だ。実際にはユニボディであることは隠されていたが、この時点では、金属切削の効率やコストがまだ今のレベルにはなく、大規模な量産テスト的な役割もあったものと思われる。
また、CPUはノートPC用のIntel Core 2 Duoだったが、Windowsマシンに先駆けてダイサイズの小さな特別版をこの製品のためだけに開発させて使っていた。しかし、ファンレスで発熱を抑えるために高負荷時に片コアを休止させてしまうため、本来の性能が発揮できず、パームレストなどがかなり熱を持つ状態だった。加えて、Micro-DVIポートもこの機種のためだけに開発されたもので、ケーブルや変換コネクタも高価で、かつ後継モデルとの互換性もなかった。
このように、初代モデルは見た目と性能のバランスがとれていなかったが、コンセプトを維持して改良を続けた結果、ベストセラーシリーズへと成長したのである。
おすすめの記事
著者プロフィール
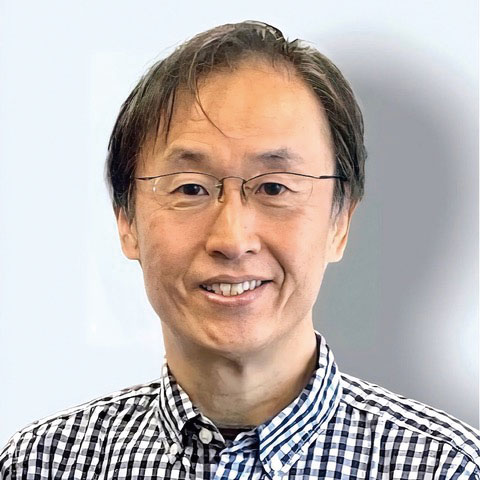
大谷和利
1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。