ジョブズの思い入れが強かったApple TV。開発途上で明かされた特異な例
今でこそApple TVは、手のひらに乗るサイズと軽さで、コンテンツも充実し、テレビがあれば1台買ってもよいと思わせる製品に成長した。しかし、2007年1月に誕生した初代モデルは、ジョブズ自らが「(Appleのビジネスにとっては)ホビーである」と公言するほど、売れない製品だった。
それもそのはずで、このときは、ストレージがSDDではなくHDDだったにもかかわらず価格が高く(日本での希望小売価格は3万6800円)、機能が限られていた。基本的にはMac、PC、iPhone、iPod touch、iPad上のiTunes Storeでレンタル、あるいは購入した楽曲や映画、保存されている写真などを、Wi-Fiまたは有線LAN経由でテレビにストリーミングするためのデバイスとして位置づけられていたが、その用途のためにわざわざ購入するほどの絶対的な魅力が感じられなかったのだ。
それでもPowerMac G4 Cubeのような製品ラインとしての中止は行わずに改良が続けられたのは、ジョブズの思い入れがそれ以上に強かったためと考えられる。その証拠に、Apple TVは同社には珍しく、まだ開発途上にあった2006年の9月に「iTV」というコードネームのプロジェクトが公開され、メディアや市場の反応を伺う動きが見られた。テレビ局からコンテンツを供給してもらうためのリードタイムが必要だったこともあるが、絶対に成功させたいという思いが込められていたのだろう。
成功のためのデザインシンキング。“ホビー”を超える存在へ
ところが現実には、前述のように初代モデルは売れなかった。ほかのスタッフの提案であれば、第1世代のみでメンテナンスモード(すなわち、製造打ち切り)の憂き目にあっていた可能性もあるが、ジョブズにはセットトップボックスの先に広がる世界が見えていたに違いない。ただ、初代モデルは、そのための解ではなかった。
その後も、地道な機能追加やストレージの拡大、値下げなどが行われたが、この間もジョブズは「ホビーである」と言い続け、製品としてはある種のステルスモード(存在してはいるものの、積極的にはアピールしない状態)になっていた。
だが、初代から3年半後の2010年9月に待望の第2世代モデルが登場し、Apple TVはついに成功のための足掛かりを得ることができた。それは、ストレージをSSDに変更するとともに、本体へのデータ保存は最小限にして、インターネットからの直接的なストリーミングを主軸にするという大きな転換だった。これにより、Mac mini並みに大きく重かった筐体は小型軽量化され、価格も8800円と大幅な引き下げに成功。現在は、ゲームにも対応させるなどの高機能化やそのためのストレージ拡大などの影響で、価格は2万1800円からと再び上昇しているものの、コンテンツの充実などと相まって、それでも十分に魅力的な製品へと成長した。
余談になるが、筆者は第2世代モデルがAirPlayに対応したことで主にプレゼンテーション用途で購入し、その後のモデルをApple TV+を楽しむメインデバイスとして愛用中だ。Appleにとっても、Apple TVはようやくホビーを超える存在になったのではないだろうか。
※この記事は『Mac Fan』2021年9月号に掲載されたものです。
おすすめの記事
著者プロフィール
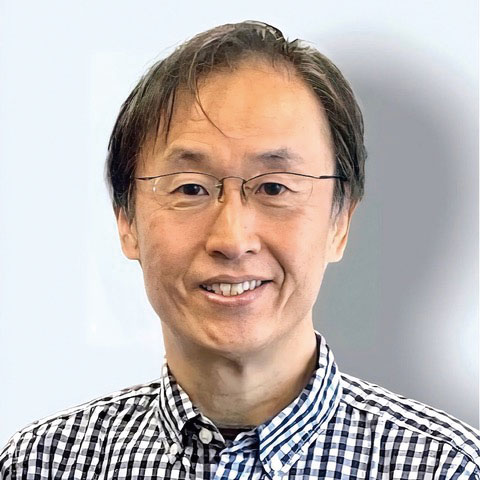
大谷和利
1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。










![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)