Appleが日本のデジタルID戦略を支援、米国の反応は?
Appleは5月30日、2025年春後半をめどに「ウォレット」でマイナンバーカードを利用できるようにする準備を進めていると発表しました。
このニュースは、米国でもデジタルID推進者や一部の識者、セキュリティ関係者の注目を集めており、日本の導入が成功すれば、米国でデジタルIDを普及させる刺激になるという期待が高まっています。
Appleが「ウォレット」で身分証明書のサポートを米国で開始したのは2021年です。日本は、Appleが身分証明書機能を米国外で初めて展開する国になります。
それなのに“先に導入された米国が日本から学ぶ”というのは「逆ではないか」と思う人が多いかもしれませんが、2024年6月時点で、米国でウォレットに運転免許証を登録できるのは4州にとどまっており、全米規模の導入にはほど遠い状態なのです。
そのため、日本での成功が示されれば、米国内でのデジタルID導入の障害が克服しやすくなると推進派は考えています。
彼らが注目しているのは、日本の発表で「物理的なマイナンバーカードが利用できる場所で、『ウォレット』に搭載したマイナンバーカードを提示することができます」と記載されていること(物理カードを持ち歩く必要がなくなる)。そして、スマートフォンにマイナンバーカードを格納することで、オンライン空間での本人認証に使える「デジタルID」になる可能性の2点です。

最初に少し説明を加えると、米国では日本のマイナンバーカードに相当するIDカードはなく、身分証明書として運転免許証もしくはパスポートを提示します。そのため「ウォレット」に運転免許証を登録できるようになったのですが、運転免許証は州の管轄下にあり、モバイル運転免許証(mDL)の導入は各州の判断に委ねられています。
同じ国の中で州によってmDLへの対応にばらつきがあるのは、身分証明手段として有用性が低いと言わざるを得ません。また、サポートしている州内であっても、常にmDLに対応してもらえるとは限らないのが現状です。たとえば交通違反の疑いで停車させられた際、専用の読み取り機が必要なのに警察官がデバイスを持っていない可能性があります。
物理カードを持ち歩かずに済んでこそのmDLなのに、活用できる場が限られ、多くのユーザーが物理カードも持ち歩いていることから利用が広がらず、そのため機材やトレーニングへの投資が進まない負の循環に陥っています。
そんな状況を打破するために、日本で物理的なカードを持ち歩かないで済む環境が実現するのなら、どのくらいの人がスマートフォンのデジタルIDウォレットを利用するのか。そのデータに興味津々というわけです。

おすすめの記事
個人番号で大失敗している米国、ID詐欺被害額は世界一
米国も州管轄の運転免許証などに頼らず、国が身分証として通用するIDカード/デジタルIDを推進すべきと思うかもしれません。しかし、国が国民のIDを管理するべきではないというのが米国の伝統的な考え方で、プライバシー保護の観点から多くの国民がそれを支持しています。
ただ、現実問題として個人を識別する手段がないと不便が生じます。そこで、米国では社会保障番号(Social Security Number:SSN)が個人番号のように使われるようになりました。
これは1935年に社会保障法が成立した際に、年金給付の記録管理のために作成された番号で、現代の個人識別に対応できるようには作られていません。そんな番号が本来の役割を超えて、納税記録、運転免許証や銀行口座の開設、雇用の記録など多くの領域で使われるようになったことが、クレジッカード詐欺やなりすましなどさまざまな犯罪の温床になっています。

プライバシー保護を主張して国民IDを手掛けず、その結果、脆弱なSSNから重要な個人情報の漏洩を多発させていては道理にかないません。米国はAppleのようなテック大手が世界のIT市場を牽引するIT先進国でありながら、デジタルを利活用する国の取り組みは他国に遅れているのです。
レガシーな制度にとらわれず、政府がリーダーシップをとって国民にIDカード/デジタルIDの利便性を提供する必要性を感じてはいるものの、さまざまな障害を乗り越えられずにいます。同じようにレガシーな制度からの変更に抵抗を持つ日本が、逆風にさらされながらもデジタル社会の実現に邁進するのを興味深く見ています。ただ、米国の民間企業と日本政府が両輪となって、それを推し進めるのを見るのは複雑な心境でもあります。
デジタルウォレット+身分証明書、ニーズ高まるオンラインでの個人証明
マイナンバーカードが入ったiPhoneでは、各種民間オンラインサービスの申込・利用が可能になる予定です。
米国のデジタルID推進派の間では、mDLのこれまでの取り組みについて、対面での身分証の提示という用途を前面に押し出したのが間違いだったという意見が広がっています。
スマートフォンに運転免許証を格納できても、運転免許証を持ち歩くことに慣れた人にはそれほどアピールしません。また、このユースケースは運転免許証で完結してしまい、スマートフォンとデジタルウォレットによるデジタルIDの新たな可能性を示せずにいます。
それよりも、オンラインにおけるアイデンティティを確立、保護、証明する方法に価値があるとし、mDLを導入した州や検討している州にオンラインでの活用に目を向けるように呼びかけ始めています。

たとえば、3月末にフロリダ州のロン・デサンティス知事が、14歳未満の子どもがソーシャルメディアのアカウントに登録することを禁止し、14~15歳には親の同意を得ることを義務づける法案に署名しました。これはソーシャルメディアが子どもの精神衛生に悪影響を及ぼす可能性があるという懸念の高まりに対応するもので、2025年1月1日に発効します。
この法案は、憲法修正第1条を根拠とする議論に直面していますが、そもそもフロリダ州政府はオンラインユーザの年齢をどのように確認するつもりなのでしょうか?
現状を考えると、誕生日を入力させるような効果に乏しい方法か、プライバシーを侵害しかねない方法のどちらかになりそうです。そしてこれは氷山の一角に過ぎません。ボットによるフェイク情報ネットワーク、ディープフェイク、その他のオンラインID詐欺を取り締まろうとする規制当局の取り組みにも同様の問題が存在します。
物理的な世界で身元証明として用いられている身分証を、仮想の世界でどのように反映できるでしょうか。オンライン上では独自のアイデンティティを確立している人が多く、インターネットの文化は実名を強制することを良しとしていません。
また、米国では匿名の言論を法律で禁じることは憲法修正第1条に反する可能性が高く、ソーシャルメディア・プラットフォームがアカウント保有者に身元と結びつけることを要求すれば、強い非難を浴びることになるでしょう。
「ウォレット」の身分証明書機能では、身元証明の際に身分証明書のすべてを見せる必要はなく、ユーザが共有する情報を事前に確認したうえで共有できます。年齢確認が必要な場合、年齢だけが要求され、ユーザが他の個人情報を渡していないことを確かめることが可能です。

現在のところ、マイナンバーカードは現実世界での身元証明に使う身分証明書です。しかし、米国での議論を鑑みると、日本においてもそう遠くない将来にオンライン空間における個人証明の議論が広がりそうです。
デジタルIDとしてマイナンバーがそうした領域にまで利用されるかどうかはまだわかりませんが、スマートフォンのデジタルIDウォレットにマイナンバーカードを格納できる日本には、より先進的なソリューションを打ち出せる可能性があります。
著者プロフィール
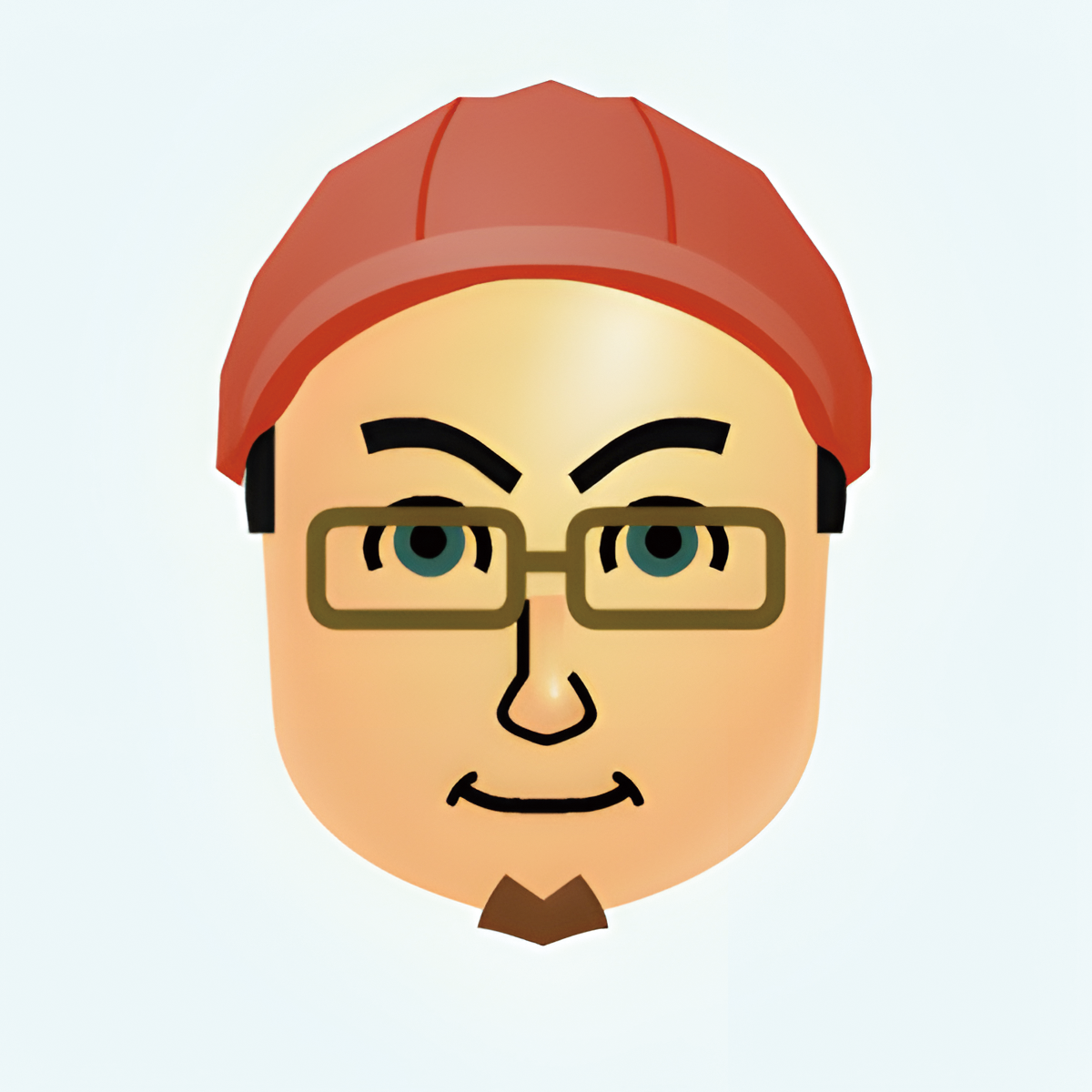






![iPhoneの「緊急地震速報」が鳴らない? 「設定」アプリの[通知]を見直そう!](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2024/06/EMERGENCY-256x192.png)

