※この記事は『Mac Fan 2018年5月号』に掲載されたものです。
2000年代に収益が大きく落ち込んだ米国の音楽産業。しかし、ここにきて回復の兆しを見せ始めている。Apple Musicなどのサブスクリプションサービスが軌道に乗るとともに、違法ダウンロードが減ってきたからだ。
なぜサブスクリプションサービスは、違法ダウンロードを駆逐することができたのか? これが今回の疑問だ。
違法ダウンロードを克服した米国音楽産業
米国の音楽産業が好調だ。2000年頃から「CDが売れない」という底なし沼にはまり、収益は右肩下がりだったが、2010年頃に下げ止まり、横ばいを維持できるようになった。そして、2016年に上昇に転じると、2017年には上昇傾向がはっきりした。


収益が下がった原因、それは違法ダウンロードが横行した影響だ。そして、収益が持ち直した原因。それはApple Musicなどのサブスクリプションサービスからの使用料収入だ。
インターネットが一般に普及して20年、音楽産業は違法ダウンロードとの戦いを続けてきた。その長い長い戦争がようやく終結する。開戦のきっかけは、1999年に登場したNapsterだった。これはいわゆるP2P型のファイル共有ソフトで、音楽CDからリッピングした音声ファイルを簡単に交換できた。
この違法ダウンロードは世界中に広まり、音楽産業は大きな打撃を受け、収益が下がり始める。しかし、音楽産業は効果的な手を打つことができなかった。なぜなら、当時は法律が追いついておらず、音楽を勝手にダウンロードすることの違法性を明確に問うことができなかったのだ。
この問題を解決しようとしたのがAppleだった。Appleは2003年にiTunes Music Storeを開設し、1曲99セントという低価格でのデジタル販売を開始した。当時CEOだったスティーブ・ジョブズは、「誰だって、万引きをした音楽を聴くのは心地良くないはずだ。利便性が高く、価格が妥当なデジタル配信があれば、そちらを利用する」と主張して、iPodの一大ブームを引き起こした。しかし、確かにデジタル配信の収入は増えていったが、それ以上にCD売り上げの落ち込みが激しく、音楽産業はさらに沈んでいく。
これを救ったのが、2008年に登場した聴き放題サブスクリプションサービスのSpotifyだった。毎月1000円程度を払うだけで、いつでもどこでもどのデバイスからも、世界中の音楽を聴くことができるという「最終兵器」だ。このサブスクの登場により、CD売り上げ減少による収益減を補えるようになり、音楽産業全体の収益は下げ止まった。さらに、2015年にAppleがApple Musicを始めると、翌年にはついに収益を上昇に転じることができた。


体験価値を提供できれば、人はお金を払う
なぜ、デジタル配信だけでは違法ダウンロードに対抗できず、サブスクでは可能だったのか。デジタル配信は、従来のCD店での購入体験をeコマースに逐語訳したものにすぎない。利便性は向上したが、まったく新しい音楽体験を提供したわけではない。それまでCDを買っていた人がデジタル配信に移行するだけで、新しい消費者を惹きつけるところまではいけなかった。もちろん、当時の技術、社会状況からすればそれでも最先端だったのだが、やはり限界があった。
一方で、Apple Musicなどのサブスクは、それまでになかったまったく新しい体験だ。数百万曲の音楽を自由に聴ける状況というのは、クラウドとインターネットという技術の賜物であり、ネット以前の社会では実現しようがなかった。今、私たちはApple Musicを単なる便利なサービスくらいにしか感じなくなってしまっているが、よくよく考えれば、人類が経験したことのない音楽体験をしていることになる。違法ダウンロードでも、さすがにこの体験まで提供できるシステムは存在しないはずだ。
こういった新しい体験が、月額約1000円を支払ってもいいと思える価値になっている。今ではサブスクのみで楽曲を公開し、ヒットを飛ばすアーティストが現れ始めている。音楽の流行の発信地すらサブスクになろうとしているのだ。
未だ違法サイトに悩まされ続ける出版業界
違法ダウンロードを克服しつつある音楽産業に対して、苦しんでいるのが出版産業だ。今、漫画や雑誌、写真集などを配信している某サイトが大きな話題となっている。このサイトは法に触れない仕組みを採用しているようで、自分で複製した漫画などをアップロードするのではなく、「複数のP2P(Peer to Peer)サーバ、クラウドなどにアップロードされている漫画本データを検索して、それを表示している」という建てつけになっている。しかも、利用者はデータをダウンロードすることなく、Web上で閲覧することができる。
以前、同様の配信サイト「フリーブックス」は、あるP2Pトレントサーバでやりとりされている出版物データを利用していた。フリーブックスの違法性を問うことは難しいが、このトレントサーバでは、明らかに違法行為が行われていた。そこで、多くの権利者がトレントサーバの管理者にそれを指摘したところ、管理者が訴訟になることを恐れて、トレントサーバを自主的に閉鎖。このトレントサーバをデータ源としていたフリーブックスも閉鎖せざるを得ないという形で、この問題は解決した。しかし、今取り沙汰されている某サイトは、複数のデータ源を利用しているようだ。
対抗策としては、検索サイトにこの配信サイトを検索対象から外してもらう、広告業者に広告配信を停止してもらうなどが考えられる。配信サイト運営者の目的は、広告を表示して広告出稿料を稼ぐことなのだから、兵糧攻めがもっとも効果があるだろう。しかし、検索サイトも広告業者も、このサイトの違法性が明確にならなければ、そのような対応をすることが難しい。現在のところ有効な解決策がなく、このままでは漫画家が育たなくなると、出版関係者は深く悩んでいる。
体験価値で消費者を惹きつける。そこにしか解決の道はない
これらはデジタル万引きにほぼ等しい行為で、少なくとも他人に自慢できるようなことではない。しかし、悩ましいのは、著作権処理をきちんと行った出版サブスクサービスよりも、この配信サイトのほうが圧倒的に魅力的という点だ。
合法サブスクの多くは、「読み放題」と謳いながらも、ラインナップは及び腰である。多くの人が読みたがる旬の漫画は配信されず、旬がすぎた漫画ばかりが並ぶ。多くの人が望んでいるのは漫画喫茶の電子版だと思うのだが、公立図書館の電子版に毎月お金を払って利用している気分になる。要は、出版社側が「お金になるコンテンツを配信してしまうと全体の収益が下がるのではないか」と腰が引けてしまっているのだ。
もちろん、当事者にとっては存続に影響する切実な問題で、外野がああしろ、こうしろと気軽に口を挟めるようなことではない。しかし、音楽産業が回復したように、出版産業が目指す道もひとつしかないだろう。軸足をサブスクに移して、違法配信サイトよりも圧倒的に体験価値の高い合法サブスクをつくるよりほかないのだ。権利者対違法配信サイトという捉え方では出口が見えることはなく、違法配信サイトとどちらが消費者をより惹きつけられるのかという同じ地平に立った競争をする以外、解決の道はないのだと思う。音楽産業は、その鮮やかな成功例を示してくれている。
おすすめの記事
著者プロフィール

牧野武文
フリーライター/ITジャーナリスト。ITビジネスやテクノロジーについて、消費者や生活者の視点からやさしく解説することに定評がある。IT関連書を中心に「玩具」「ゲーム」「文学」など、さまざまなジャンルの書籍を幅広く執筆。


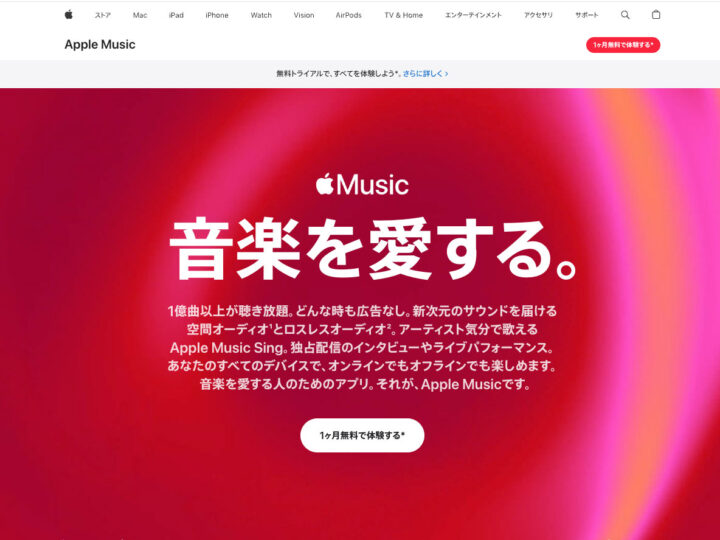



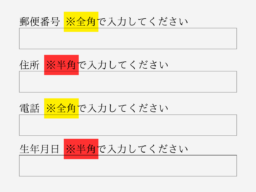



![アプリ完成間近! 歩数連動・誕生日メッセージ・タイマー機能など“こだわり”を凝縮/松澤ネキがアプリ開発に挑戦![仕上げ編]【Claris FileMaker 選手権 2025】](https://macfan.book.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/10/IMG_1097-256x192.jpg)