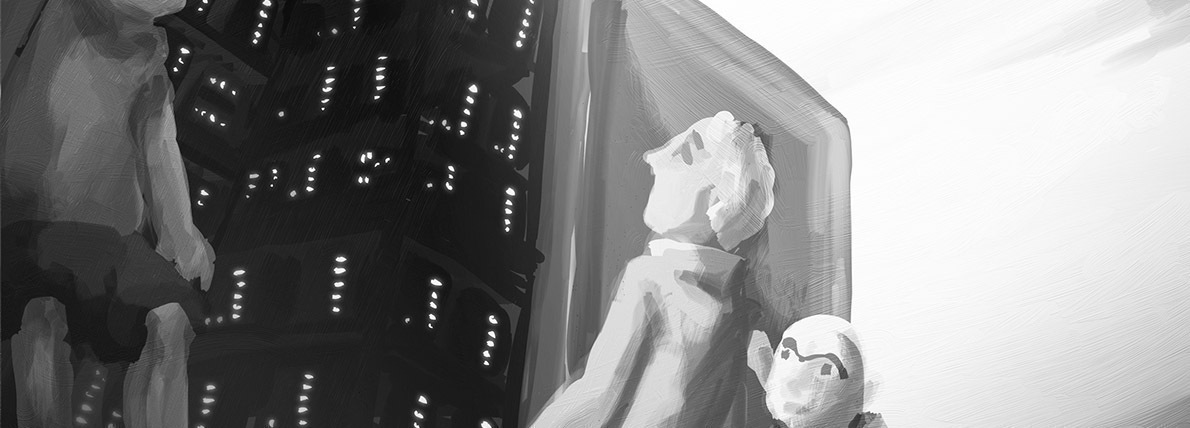イラスト/灯夢(デジタルノイズ)
「三十二ペタバイト……凄いな。ありがとうよ、ジャンボさん」
トレーラーのだだっ広い運転席と助手席の間にMacBookを広げて置いた男が口笛を吹いた。ペタバイト級のストレージを調達するよう依頼してきた、ジェラルド・バウアーだ。
「三十二ペタ、フルには使えないから気をつけてくれよ」
おれは背後を親指で指した。トレーラーヘッドが牽引するのは、十二本のサーバーラックを満載したコンテナだ。
「Drobo(ドゥロボ)5Dを五百十二台。これをXsanで束ねてマウントしてあるが、ハードディスクは千本しか刺さってない。これだけあると週に一つはクラッシュするから、予備のHDDも二百本ほど積んどいた。ダッシュボードにアラートが出たら、ランプの付いたHDDを交換すればいい」
頷きながら「助かる、助かるよ」と繰り返したジェラルドへおれは言った。
「助かるのはアメリカだろう?」
「その通りだ」
ジェラルドはドアポケットから米国の地図をとりだしてハンドルに押しつけた。地図には、出発地点のミシガン─寂れた工業地帯からボストンへ向かい、ニューヨーク、ワシントンDC、リッチモンドなどの東海岸の主要な都市を辿ってフロリダ半島の根元であるジャクソンビルで西に向かうルートが描かれていた。南部を西に向かうルートは途中で南に折れ、メキシコとの国境を越える場所まで描かれていた。そこは、壁がどうしても建設できない場所だった。
「まさか国境を跨ぐインディア−−」
「居留地を通るときはその言葉を使うなよ。パパゴ族もだめだ。あれはスペイン人の征服者たちが豆のような奴ら、という意味でつけた名前だ。彼らは自分自身を〝トホノ・オ=オダム〟と呼ぶ」
口を尖らせながら頷いたジェラルドにおれは念を押した。
「居留地に着いたらアレフという男を呼べ。長老の側近だ。そいつに金を払っておいた。トレーラーで国境を越えられる場所を案内してくれる」
ジェラルドの旅は過酷だ。彼は三ヶ月ほどかけて主要都市を巡り、ホットスポットからアメリカ政府が公開しているすべての情報をダウンロードしてDroboに蓄え、メキシコへ向かう。
「幸運を祈るよ」
おれはジェラルドの肩を叩いて、高い助手席から地面に下りた。運転席でハンドルを握ったジェラルドは、いつのまにか赤いキャップを被っていた。キャップの額には白い糸で《グレート・アメリカ・アゲイン》と刺繍されていた。
おれは笑った。
「いい偽装だな! 狂った大統領からオープンガバメントのデータを救おうとしているなんて誰も思わないさ」
ジェラルドはふっと笑って窓を閉め、五百馬力を絞り出すキャタピラー社製のC15エンジンに火を入れた。空気を震わせる咆哮に続いてコンテナを牽いたトレーラーが動き出す。
あわてた避けたおれの目の前を通り過ぎていくジェラルドは、なぜか歯を食いしばっているように見えた。
*
おれは砂漠のキャンプに呼び出された。渡しておいた賄賂が長老にばれてしまい、ジェラルドともども、メキシコへ行く理由を直接話すことになったのだ。
キャンプでは、砂漠を横切る国境のフェンスを撤去しているところだった。
車から降りたおれに、野暮ったいスーツを着た初老の男性が歩み寄ってきた。もしも街のスターバックスで彼を見かけ、ターコイズをあしらったループタイに気づいたとしても、ネイティブアメリカンの関係者だとは思わなかっただろう。そんな普通の男性だった。
「ようこそ」と言っておれの手を握った長老は西の地平を眺めた。
「一九九八年まで、わたしたちは国境を自由に行き来できた。大統領が時計を逆に回したいのなら、わたしたちも同じことをやるだけだ。あの山の向こうでは、ぶ厚くて高い壁を作ろうとしている−−まあ、知ってるか」
「現場は見てきたよ。壁の支持者と反対派が睨み合ってた」
長老は人好きのする笑顔を向けた。
「つまり、ジェラルドさんとやらがメキシコ側に抜けるには、この居留地を通るしかないということだーーあれかな?」
おれは頷いた。
北から、盛大な土煙を上げて走ってくるのは三ヶ月前にボストンで別れたジェラルドのトレーラーだった。
トレーラーを止めたジェラルドは、おれの姿に首を傾げて運転席から降り立った。三ヶ月の旅を経て白かった頬は日に灼け、無精髭に覆われていた。
「ジャンボさん、どうしてここに?」
「賄賂が通用しなかったんだ。こちらがトホノ・オ=アダムの長老だ」
握手を求められた長老は首を振った。
「だめだ。彼の支持者は通さない」
「彼は違う。なあ、ジェラルドさん。帽子を捨てて、あなたは違うって証明してやってくれよ」
ジェラルドは帽子の鍔を撫でた。
「おれは彼に投票した」
「なんだって?」
叫んだおれの横で長老はゆっくりと、しかし力強く北を指さした。
「戻りなさい。五十キロも行けば、君の大好きなアメリカに帰れる」
「おい、ジェラルド。今は後悔してるんだよな」
おれにジェラルドは首を振った。
「いや、必要だった。寂れた街に住むおれたちが声をあげる、最後のチャンスだったんだ」
「確かにな」と、ため息をついた長老はゆったりと腕を組んで言った。「二〇二〇年の国勢調査で大統領選挙人の構成が変わる。昨年彼を勝たせた支持者全員が再び彼に投票しても勝てないだろう。それで、どうだった? 勝たせて」
ジェラルドは顔をしかめた。
「やつはバカだった」
「分かってたことじゃないか」
「程度の問題だ! オープンガバメントを全部逆転させるなんて誰が想像できる。data.gov(データ・ドット・ゴヴ)もFlickrにアップされた写真も、機密の解かれた公文書も全部公開停止だ!」
「オープンガバメント? 君は--」
「おれはアメリカを保存した。可能な限りの文書を持ってきたよ。二十ペタバイトの歴史だ。頼む。通してくれ」
長老は首を振った。
「だめだな」
「どうして!」
「データはわたしたちが預かる。ジャンボさん、メンテナンスする方法を教えてくれないか」
「構わないが……」
コンテナに視線を向けた長老はにこりと笑った。
「オープンガバメントが公開した公文書には、アメリカ政府がこの土地を勝手に売り買いしたときの記録が残っている。先祖の写真もだ。前の大統領が公開してくれたとき、どれほど嬉しかったことか。それが失われようとしていたのか」
ジェラルドは我に返ったかのように口を開いた。
「……だから、おれがメキシコに持っていくよ。オープンガバメントが再開したら、データを提供する」
「あなたは帰るんだ」
長老はジェラルドの通ってきた道を指さした。
「そして二〇二〇年、今度はまともな方へ投票してくれないか」
藤井太洋
2012年、セルフパブリッシングの『Gene Mapper』でデビュー。『オービタル・クラウド』で第35回日本SF大賞、第46回星雲賞日本長編部門を受賞。