去る12月8日は、「コンピュータマウスの誕生日」とされる日だった。
米国時間の1968年のこの日、コンピュータ科学者のダグラス・エンゲルバートが、初めて公共の場でマウスをお披露目し、のちのデスクトッププレゼンテーションにつながるようなデモを行ったからだ。
今では、筆者も含めて、トラックパッドで事足りている人も多いと思うが、かつてはマウスこそが、GUIベースのパーソナルピュータの操作には必須のポインティングデバイスであった。今では100円ショップでも販売されるほどありふれた存在のマウスだが、その起源は半世紀以上前のエンゲルバートの「木製の箱」にまで遡る。
ここでは、コンピュータ用マウスの歴史を振り返るとともに、筆者が自作したエンゲルバートのレプリカマウスを紹介する。
黎明期:木製の箱と二つの車輪
マウスの歴史は、1960年代のアメリカ、スタンフォード研究所(SRI)から始まる。当時、SRIの研究者だったダグラス・エンゲルバートが、人間とコンピュータの知的相互作用を拡張するための研究の一環として、ポインティングデバイスという概念を考案したのだ。
テキストベースのコマンドは、今の生成AIのプロンプトに似て、細かな指示を出すには適していても、画面上の位置を直感的に示すには向いていない。また、何行目の何文字目や、X方向に〇〇ピクセルでY方向に⬜︎⬜︎ピクセルのように指定できても、カーソルをそこまで持っていくためには、矢印キーを押し続ける必要があり、時間がかかっていた。
1968年12月8日、後に「すべてのデモの母(The Mother of All Demos)」と称される伝説的なプレゼンテーションにおいて、エンゲルバートは世界初となるマウスを公開した。
当時の試作機は現在のものとは大きく異なり、武骨な木製の箱であった。底面には金属製の円盤(車輪)が2つ付いており、それぞれがX軸(横)とY軸(縦)の動きを検知する仕組みで、画面上のどこにでもポインタを自由に素早く動かして、そこにある情報を指し示すことができた。
「マウス」の名は、今と違って装置の後ろから伸びるコードがネズミの尻尾のように見えたために、研究者たちの間で使われた愛称だったが、それが定着したのである。

しかし、今回の記事を書くにあたり、そのエンゲルバートのデモの動画を見直したところ、操作しているマウスは、上のものとは少し異なってきることに気がついた。それほど鮮明ではない画像だが、白いユニットも黒っぽいユニットも手のひらになじむように手前がすぼまっており、後者はケーブルが前から伸びているほかボタンも3つある点で、明らかに異なっている。
つまり、現存する、筐体が直方体のマウスは、確かに最初のプロトタイプだと考えられるが、デモで使用された改良型のユニットとは別物で、それらよりも前に開発されたものなのだろう。となると、実際のマウスが誕生した日は、12月8日よりもかなり以前のことだったと思われる。

ボール式マウスの誕生とApple純正マウス
エンゲルバートの同僚であったビル・イングリッシュは、1970年代初頭にゼロックスのパロアルト研究所(PARC)へ移籍し、そこでマウスの改良を行った。彼は、動きの自由度が低かった2つの車輪を廃止し、代わりに一つの「ボール」を搭載した。
この「ボール式マウス」は、ボールが底面を転がる動きを内部のローラーが検知することで、全方向へのスムースな移動を可能にし、ゼロックスが開発した革新的なコンピュータ「Alto」に採用されたものの、それはあくまでも実験機であったことから、一般に販売されることはなかった。
マウスが一般的なポインティングデバイスとして認められるようになったのは、Appleの功績が大きい。1979年、パロアルト研究所を訪れたスティーブ・ジョブズは、そこで見たGUIとマウスに衝撃を受けた。しかし、そのマウスが複雑ゆえに高価であることを問題視し、Macintoshの前身であるLisaのために、構造を単純化してコストを大幅に下げたものを開発するよう指示した。
ただし、当時のApple社内にはそのための技術的なノウハウがなかったため、日本のアルプス電気に開発を依頼。その結果生まれたのが、1983年のLisa、そして1984年のMacintoshにバンドルされたワンボタンマウスだった。

Photo●Marcin Wichary | CC Attribution 2.0 Generic

Photo●Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0

【URL(http://www.allaboutapple.com/
Photo●CC Attribution-Share Alike 2.5 Italy
デスクトップパブリッシングの推進役としてMacintoshが成功したことで、画面上のアイコンをクリックして操作するGUIベースのコンピュータが一般にも知られるようになり、マウスは誰もが使えるポインティングデバイスとしての地位を確立する。そして、Windowsの普及とともにマウスはさらに日常的な存在となって、世界中に浸透していった。
Macintoshのマウスドライバは、完成度がWindowsよりもはるかに高く、素早く動かすと移動距離が大きくなり、ゆっくり動かすと精密なポインティングができるなど、優れた操作性を発揮したが、その後もAppleは改良の手を緩めずに、マウスのハードウェアの改良も継続的に行っていく。
たとえば、Macintosh SEとMacintosh IIでI/OポートにADB(Apple Desktop Bus)を採用した際には、本体のデザインも担当したfrog designによってマウスのデザインも変更され、より薄く軽いものとなった。
また、その改良型では、デザイン言語の変更に合わせて丸みを帯びた形状になるとともに、ボールの位置を前寄りに変更することで、より指先に近づけ、一層、細かいコントロールがしやすい工夫がなされた。


Photo●Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0
さらに、Apple初のUSBポート搭載機となった初代iMacのデザインに合わせて開発されたUSBマウスは、画期的なツートーンの円形筐体だった。しかし、このときには、他の製品との違いを最大限に打ち出すことで、Appleのブランドイメージを復活させることを主眼としたため、スタイリング偏重気味になり、手元を見ないと前後の区別が付きにくいとの批判を受けてしまった。のちに、ボタンに窪みをつけて指先の感触で前後がわかるようにしたが、デザインを担当したジョナサン・アイブには珍しい勇み足だといえた。

Photo●Rama & Musée Bolo/CC Attribution-Share Alike 2.0 fr
機械式から光学式へ
ところで、1990年代まで主流だったボール式マウスには、大きな弱点があった。ボールが机の上の埃や皮脂を巻き込み、内部のローラーに汚れが付着して動きが悪くなるのだ。そのため、ユーザは定期的にマウスのボールを外して、内部の掃除をする必要があった。
この問題を解決したのが、光学式マウスである。1999年に、Microsoftが発売したIntelliMouse Explorerがきっかけとなり、底面のLEDとセンサーで動きを検知する方式が一般化していった。この光学式マウスによって、マウスパッドが必須ではなくなり、メンテナンスフリーの快適な操作環境が実現した。そして、より高精度なレーザーセンサーや、ガラス面でも使えるBlueTrack技術などが開発され、追従性は飛躍的に向上していったのである。また、接続方式も有線から無線(RF方式、Bluetooth)へと進化し、ケーブルの煩わしさからも解放された。
Appleも、2000年に光学式のApple Pro Mouseを発売したが、そのデザインは一見するとボタンレスに思える画期的なもので、これ以降の純正マウスも独立したボタンを設けずに、外装や上面全体がその役割を果たす機構が踏襲されていった。

Photo●Roblazek | Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5
さらに、マウスの操作性を向上させるためのトレンドとなっていたスクロールホイールについても、Appleは独自のアイデアを投入していく。Apple Mighty Mouseで、ホイールではなくボール型のコントローラーであるスクロールボールを採用することで、より自由度の高いスクロールを実現したのだ。加えて、左右の指を置く場所も押し込むとサイドボタンとして機能するスクイーズボタンになっており、いわゆるマルチボタンマウスにもなっていた。
ただし、スクロールボールにも機械式マウスのボールと同じ汚れが付着する問題があったため、現行のApple Magic Mouseでは、スクロールも上面のタッチサーフェスで行う方式になり、スタイリッシュで滑らかな形状を実現している。

Photo●Quark67 | CC Attribution-Share Alike 2.5 Generic)

Photo●Yutaka Tsutano / Creative Commons Attribution 2.0 Generic
近年は、ノートPCのタッチパッドやタブレットのタッチスクリーンの普及によって、マウス不要論がささやかれることもある。しかし、デザイン、動画編集、ゲーム、詳細なデータ処理など、精密な操作が求められる分野においては、依然としてマウスを愛用するユーザーが多く存在している。特に、Eスポーツの分野では、プロゲーマーの要求に応えて、超高解像度のセンサーや多数のプログラム可能なボタン、軽量化を追求したゲーミングマウスが活躍しており、その形も有機的で未来感を演出した派手なものになっている。
エンゲルバートのレプリカマウスを作る
ということで、以前からエンゲルバートのマウスのレプリカを作ってみたいという気持ちはあったのだが、他にもいろいろと作りたいもののアイデアがあり、後手に回っていた。しかし、写真から生成AIによって3Dモデルを作る技術も進んだことや、本来のメカニズムにこだわらずに、外観と機能性だけを模すのであれば比較的簡単であることから、着手したのである。
まず、元のマウスの写真を元に、Tripo 3Dという生成AIサービスで3Dデータを作ったのだが、あえて正面の一部が欠けたバージョンを再現している。中身はダイソーの税抜き300円の光学式ワイヤレスマウスであり、この製品のカバーを外し、メインボタンのスイッチから配線を伸ばして、別途購入した赤いボタン付きのメカニカルスイッチにつなぐことにした。また、3Dモデルの縦横のサイズは、このダイソーのマウスに合わせて調整している。
11.TinkerCAD.jpg

実際にレプリカを作り、使ってみて意外だったのは、一見すると使いにくそうな赤いボタンの位置が、この形状とサイズ感のマウスの場合には、しっくりくることだった。実は、マウスは300円だが、このメカニカルスイッチの価格は650円と、こちらのほうが高いのである。それだけにクリック感は良好で、耐久性も高そうに思える。いずれにしても、1000円弱の材料費で、このレプリカマウスを作ることができた。



偉大な発明をしたダグラス・エンゲルバートは、2013年に惜しまれながら亡くなられたが、もし存命であれば、現在のマウスのの機構と価格の安さに驚いたことだろう。しかし、その歴史は、すべて、あの小さな手作りの木箱から始まったのである。
著者プロフィール
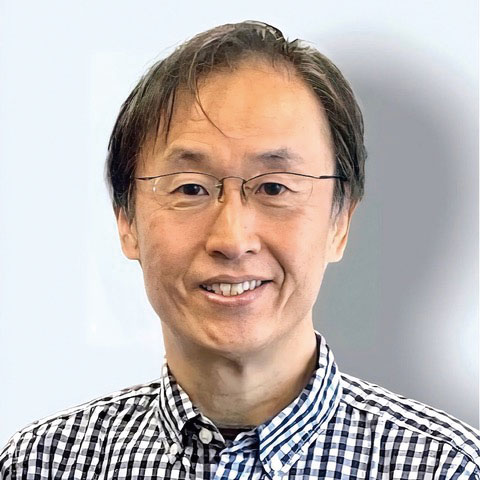
大谷和利
1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。





