Appleらしい斬新な円筒形ボディ
第2世代のMac Proは、Late 2013モデルに始まり、基本設計を踏襲しながら2019年まで続いた。第1世代モデルは、内部設計こそ一新されていたものの、Power Mac G5の筐体が流用されており、外観を含めたフルモデルチェンジが期待されていた。そのため、大幅に小型化され、かつAppleらしい斬新な円筒形ボディのLate 2013モデルには、大きな関心が寄せられた。
その年のWWDC(世界開発者会議)でプレビューされたとき、当時のワールドワイドマーケティング担当上級副社長(現Appleフェロー)のフィル・シラーは、CPU、GPU、メモリボードのすべてが「ユニファイドサーマルコア」を中心に配置されていると説明した。簡単にいえば、筐体の中央を縦に貫くダクトに大容量ファンで送風して冷却する仕組みだが、シラーは「名前だけでも凄そうだ」と笑った。そして、新世代のIntel Xeonプロセッサを搭載することで、前モデル比で最大2倍の性能を実現したと誇らしげに語ったのである。
しかし、その一方、開発者やアナリストの間では発表の時点ですでに懸念が表明されていた。メインユーザであるプロのクリエイターは、高度で複雑な処理や大量のデータを扱うために、数多くの周辺機器をつなげたり、拡張カードを利用する必要がある。だが、Mac Proのコンパクトな筐体には、そのための拡張性が明らかに不足していた。
シラーは、技術が進化した今だからこそ、MacBook AirのようにデスクトップMacもフォームファクター(主要システム部品の物理寸法やレイアウト)を変えるべきときだとしてMac Proのサイズの意義を強調したが、のちにAppleも拡張性不足を認めざるを得なくなり、第3世代モデルでは再びタワー筐体へと戻ることになる。
精緻な構造にジョブズの影
ただ、シラーの主張にも一理はあった。FireWireポートなどを介して周辺機器や外部GPUユニットを接続できれば、内部拡張の余地が限られていてもニーズに対応でき、それらが不要なプロシューマは本体のみで場所をとらずに使えることがメリットになるというわけだ。しかし、問題は、そうした周辺機器が揃わないことや、機器があってもMac対応のドライバがないことだった。素晴らしい本体を作ればサードパーティがサポートしてくれるはずと期待したわけだが、その実、本体が普及しないことにはサードパーティも対応できないという「ニワトリとタマゴの状態」になったのだ。
Mac Proはハイエンドマシンだが、基本的な発想は、かつてジョブズの肝煎りで開発した(やはりビジネス的には失敗した)Power Mac G4 Cubeに似たところがあった。内部拡張を制限したクローズドな構造に、それまでのコンピュータにはない画期的な外装デザインを与えるというやり方である。
これは推測だが、外観と内部構造をここまで突き詰めたマシンを出すには、数年前から開発を始めていたと考えるのが妥当であり、そうなると2011年に亡くなったジョブズの意向が色濃く反映されていた可能性が高い。だとすれば、拡張性を犠牲にしても、彼が夢見たクローズドな高性能Macの実現に、ティム・クック以下Appleのスタッフが一丸となって取り組んだ製品が、第2世代のMac Proだったのでは、とも思うのだ。
※この記事は『Mac Fan』2024年1月号に掲載されたものです。
著者プロフィール
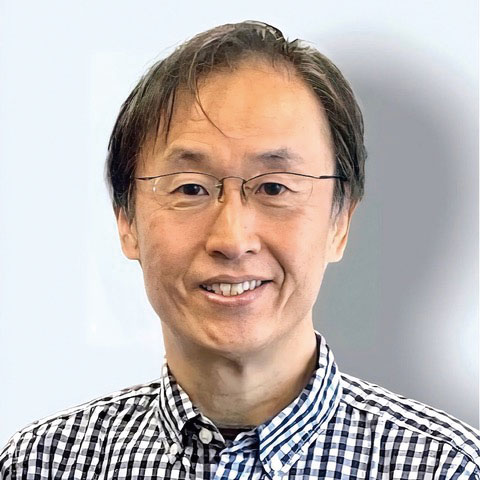
大谷和利
1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。




