広大な作業エリアと視野角の広さが魅力だった
折しも、AppleはWWDC23で「Apple Vision Pro」を発表し、「空間コンピューティング」という新概念を打ち出した。目の前の空間に、巨大なウインドウを複数出現させ、それをわずかなジェスチャや声、バーチャル&リアルのキーボードなどで自在に操れる、次世代のコンピュータ環境だ。一方で、2004年に発売された「Apple Cinema HD Display」の30インチモデルは、その前に座ると視野の大半が画面で占められるという意味で、当時の空間コンピューティング的なデバイスだったともいえる。
もちろん、自由度の低い据え置き型で、直接的な操作もできない単なる表示装置だったわけだが、その広大な作業エリアと視野角の広さ(水平・垂直方向に170度ずつ。後期型は同178度)、輝度(270 cd/m2。後期型は400 cd/m2)、コントラスト比(400:1。後期型は700:1)は、プロのデザイナーやプロシューマーユーザの憧れだった。その頃のApple純正LCDディスプレイは、20インチ未満のモデルが「Studio Display」、20インチ以上のモデルが「Cinema Display」として区別され、解像度がフルHD以上になると「Apple Cinema HD Display」と呼ばれた。インチサイズでは、23インチと30(実質29.7)インチモデルのみがApple Cinema HD Displayに該当した。
とはいえ、解像度はiPhone 14 Pro Max並み
Apple Cinema HD Displayの30インチモデルは、2560×1600ピクセルという高解像度を誇っていたのだが、これを最新のApple製品と比べると、何と画面サイズが6.7インチのiPhone 14 Pro Maxとあまり変わりがない。細かくいえば、iPhone 14 Pro Maxの長辺は2796ピクセルで236ピクセル多く、短辺は1290ピクセルで310ピクセル少ないが、もし縦横比が同じならば、完全にiPhoneの勝ちなのである。
当時の資料には「このディスプレイを2台並べることで、800万ピクセルという驚くべき画面を手に入れることができるのです」と書かれており、2台並べれば、さらに空間コンピューティング的な光景が目の前に広がるわけであった。とはいえ、このディスプレイは、1台あたりの本体価格が37万9800円で2台なら75万9600円となり、さらに貨幣価値の違いを考えると、今日では1台40万円、2台で80万円程度の感覚になる。
実際にこのディスプレイを駆動するには、2系統のDVIケーブル接続が必要であり、Power Macに加えて、高解像度デュアルリンクインターフェイスを備えたグラフィックカードが必要なので、トータル金額は、軽くその倍を超えただろう。それと比較すれば、Vision Proの3499ドル(50万円弱)という価格設定が、安く感じられてしまうほどだ。
Apple Cinema HD Displayは上位のモデルのみ、従来からの独自規格の映像端子であるADCではなく、業界標準であるDVI端子が採用されたため、Windows PCも接続できた。純正ディスプレイは、この後、「Apple LED Cinema Display」、「Apple Thunderbolt Display」を経て「Apple Pro Display XDR」へと発展したが、この種の大型モニタが廃番となったときが、真の空間コンピューティングの完成なのかもしれない。
※この記事は『Mac Fan』2023年8月号に掲載されたものです。
著者プロフィール
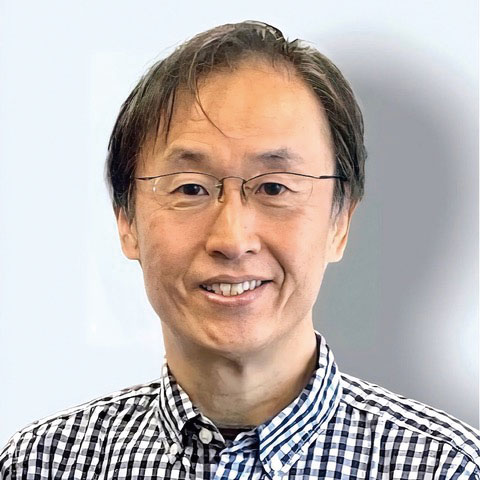
大谷和利
1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。





