iMacの最上位モデル、iMac Pro
2017年の末にデビューし、当時のiMacの最上位モデルとなった製品が、このiMac Proである。
その頃Intel CPUの高性能化、高効率化が頭打ちとなりつつあったことから、Appleは本来の最上位機種であるMac Proをなかなかモデルチェンジすることができずにいた。そこで同社は、拡張性が乏しいものの、27インチのRetina 5Kディスプレイ(5120×2880ピクセル)と、Intel Xeon Wプロセッサ(8/10/14/18コア)、4つのThunderbolt 3ポート、10ギガビットイーサネット端子などを搭載したiMac Proを用意したというわけだ。カラーも通常のiMacのシルバーとは異なるスペースグレイを採用することで特別感を演出。買い替えや新規購入に踏み切れずにいたMac Proのオーナーや潜在ユーザに対して、別の選択肢を与えたのである。
一体型の省スペースマシンながら、Mac Proに匹敵する性能を叩き出すiMac Proは、海外の紹介記事では「ビースト(野獣)」とも呼ばれ、日本では「羊の皮を被った狼」的な受け取られ方をした。拡張性がないことから、購入者の心理としてなるべく最初に高スペックのモデルを買っておこうとする意識が働くため、Appleにとっては、かえって好都合なパッケージングだったかもしれない。
更新も後継機もない、孤高の1台
とはいえ、最低構成でも55万8800円、ハイエンドのBTO構成では本体のみで優に160万円を超える価格設定だったので、誰もが気軽に買えるモデルではなかった。つまり、iMac Proは完全にプロ向けの製品だったわけだが、これを一気に300台も社員に貸与しようとする企業があり、話題を呼んだ。計2億円弱の予算を用意して、その施策に踏み切ったのは、転職サイト「ビズリーチ」を運営する株式会社ビズリーチだった。
理由は、それまでエンジニアが使っていたMacBook Proに比べてアプリのビルド時間が4分の1程度で済むためで、コストがかかっても開発効率を上げることを最優先したのである。エンジニアとデザイナーが全社員の3割弱を占める同社では、Linuxサーバ+macOSによる開発環境がグローバルスタンダードであると考えており、元よりWindows PCという選択肢はない。そして、世界に通用する一流の人材を育てるための投資を惜しまずに行うことが、会社のポリシーとなっている。
ちなみに同社では、Mac、Swift、iOSがエンジニアの「三種の神器」的な存在になっていて、希望すれば、iMac Proに加えて、持ち運びができるMacBook Proも貸与されてデュアルマシン環境を構築できるという贅沢な体制が敷かれていた。
このように、一部ではその価値が大いに評価されたiMac Proだったが、2020年に27インチモデルのiMacがアップデートされて最大10コアのCPUが選択可能になると、両製品の性能差は縮まっていった。そのためiMac Proの存在意義は次第に薄れていき、翌2021年の3月に販売終了の憂き目を見た。現在、直接の後継機はないが、M2 Maxチップや、来るべきM3チップを搭載したiMac Proの復活を渇望している人や企業は、確実にあるに違いない。
著者プロフィール
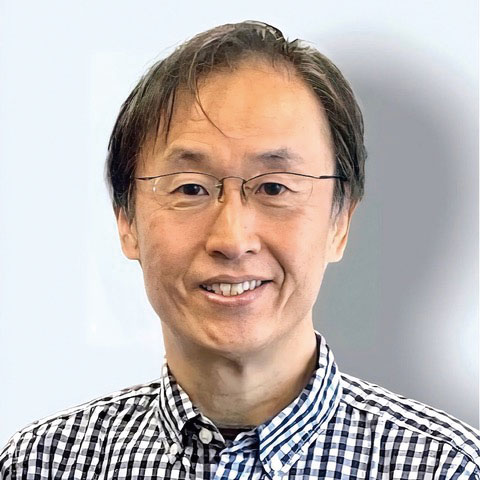
大谷和利
1958年東京都生まれ。テクノロジーライター、私設アップル・エバンジェリスト、神保町AssistOn(www.assiston.co.jp)取締役。スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツへのインタビューを含むコンピュータ専門誌への執筆をはじめ、企業のデザイン部門の取材、製品企画のコンサルティングを行っている。



