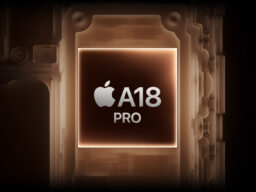※本記事は『Mac Fan』2023年3月号に掲載されたものです。
– 読む前に覚えておきたい用語-
| Time Machine | M-DISC(Millennial Disc) | RAID(Redundant Array of Independent Disks) |
|---|---|---|
| macOSに標準搭載されているバックアップ機能。最小1時間単位の自動増分バックアップを実現し、容量の許す限り過去に削除したファイルやフォルダも復元できる。別のMacへの環境移行機能「移行アシスタント」にも利用できる。 | 米Millenniata社が開発した長寿命を謳う追記型光ディスク。無機系記録層に高出力レーザで記録を行うため、書き込みにはM-DISC対応ドライブが必要だが、読み出しは一般的なドライブで可能。DVD-RとBD-Rメディアが製品化されている。 | ディスクアレイとも呼ばれ、複数のドライブにデータを分散して記録することで、高速性(RAID-0)や冗長性(RAID-1、RAID-5、RAID-6)を向上させることができる。サーバシステムなど大規模なストレージで採用されることが多い。 |
Apple製品のデータバックアップの重要性
Apple製品(デバイス)に記録されたデータには、さまざまなバックアップ手段が用意されている。MacやiPhone、iPadなどのバックアップにはクラウドサービスであるiCloudが用意されているほか、Macに完全なバックアップを行うこともできる。そのMacにはTime Machineバックアップ機能が標準装備されているほか、サードパーティー製のバックアップソフトなど、ユーザデータの保全(保管)にはさまざまな手段がある。

バックアップの目的は、不慮のトラブル(障害)から大切なユーザデータの消失を防ぐこと、そしてシステムやデバイスを継続的に使い続けるための「可用性」の担保だ。すべてのデータのバックアップが確保されていれば、仮にデバイスが故障した場合でも新しいデバイスに全データ(システムやアプリを含む)を引き継ぐことでデータの喪失を回避し、システムやデバイスを利用できない時間(ダウンタイム)を最小限に抑えることができる。
データ消失をともなうトラブルにはさまざまなケースがあるが、もっとも一般的なのはデバイスの故障だろう。「調子が悪い」といったレベルの障害から「電源が入らない」といった深刻なケースまであるが、いずれにしてもあらゆるデバイスはいつか「必ず」壊れるのは間違いない。データを記録しているのはストレージと呼ばれる記録媒体で、現在のApple製品は例外なくNANDフラッシュメモリをそのストレージに使用しており、そのほとんどがロジックボードに直接実装されていて取り外すことができない。

画像:iFixit
従ってデバイス本体やストレージが故障した場合、そこに格納されたデータはサルベージ(復旧)が不可能になる。そこで失っては困るデータは、外部に接続された別のストレージやクラウド上のサービスにバックアップしておくことが必要だ。さらにランサムウェアをはじめとする「悪意あるソフトウェア」によって、データの消失や改ざんが発生するリスクも近年増加しており、バックアップの重要性が一層高まっている。
データを長期保管するには? 目的別に選ぶストレージのポイント
バックアップを確保するうえで大切なことは、それを保管するストレージの種類を目的や用途に合わせて選択することだ。ストレージにはSSD、HDD(ハードディスク)、メモリカード、光メディア、クラウドサービスなどさまざまだが、いずれもメリットとデメリットが存在する。
まずMacやiPhone、iPadのストレージと同じNANDフラッシュメモリを記録媒体とするSSDやメモリカードは、高速アクセスが可能でバックアップに必要な時間が短く、温度変化や衝撃などの環境変化に強い特徴を持つ。その一方でTBW(総書き込み容量)という明確な寿命があり、寿命に近づくにつれてデータ保持期間も短くなる。つまり頻繁なバックアップやデータの長期保管には適さないストレージだ。したがって長期バックアップ用途では他のストレージと組み合わせて運用することが好ましい。
SSDが普及するまでストレージの代表だったHDDは、高速性と優れたデータ保管性を兼ね備えており、SSDのような書き換えによる劣化もほとんどない。一方で稼働中の衝撃や振動に弱く、複雑なメカニズムを持つことから部品の摩耗や経年劣化による故障リスクがある。SSDの弱点を補完でき、かつ容量あたりのコストが低いことから、iMacやMac miniなどのデスクトップMacのTime Machineバックアップ先として最適だ。
一方、写真や動画などの個人的かつ唯一無二のデータを保管するのに適しているのが光メディアだ。CDやDVD、BlueRayなどの光メディアは耐環境性や保管性に優れており、直射日光や高温多湿を避ければ10年以上の保管に耐える(M-DISCのように100年以上の耐久性を謳うメディアもある)。特定の機種やOSに依存しないため、ISO–9660やUDFなどの汎用フォーマットで記録することで、次世代機種でのアクセス性も期待できる。さらにDisc at Onceで記録することでデータの変更や削除ができなくなるため、誤操作などによるデータ喪失リスクが低い点でも長期保管に適している。

iCloudやGoogleドライブなどのクラウドサービスはストレージのメンテナンスを行う必要がなく、デバイスや利用場所を選ばず、インターネットを利用できる環境であればいつでもどこでも利用できるメリットがある。一方で大容量サービスは有料な点や通信にともなうコスト負担も必要だ。各社のクラウドサービスは万全のバックアップ体制を採っているとはいえ、データの管理はユーザ責任でありサービス提供者はデータの安全性を保証しない。そのサービスが永久的なものではないことも踏まえると重要なデータのバックアップをクラウドのみに頼るのは危険であり、他のローカルストレージとの併用がおすすめだ。

RAIDへの幻想と現実
データのバックアップで重要なのが冗長性の確保だ。冗長性とはシステム異常時に機能を維持するための仕組みで、ストレージの場合はドライブを多重化することでデータの安全性を高めるRAIDシステムが名高い。RAID−1やRAID−5では複数のドライブ(HDDやSSD)を組み合わせ使うことで、そのうちの1台が故障してもデータの喪失を防げる。大規模なサーバシステムでは多数のドライブをRAID構成で扱い、システム稼働中でも故障したドライブのみを交換することで、システムをダウンさせることなく継続的な利用ができるのが大きな特徴だ。
個人向けの外付けストレージやNAS(ネットワークストレージ)でもRAID構成の製品があり、ドライブの故障によるデータの喪失を回避できる。ただしRAIDシステムは決して「故障しないストレージ」ではないので過信は禁物。冗長性が発揮されるのはあくまでドライブの故障のみで、ドライブ以外の部位の故障やファイルシステムの障害には無力だ。したがって冗長性を求めるなら、バックアップ先のストレージを2台に増やすほうが確実だ。パーソナルユースでは単一のRAIDストレージでドライブ冗長性を高めるより、種類の異なるストレージを組み合わせて利用するほうが安全だと言えるだろう。
著者プロフィール